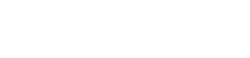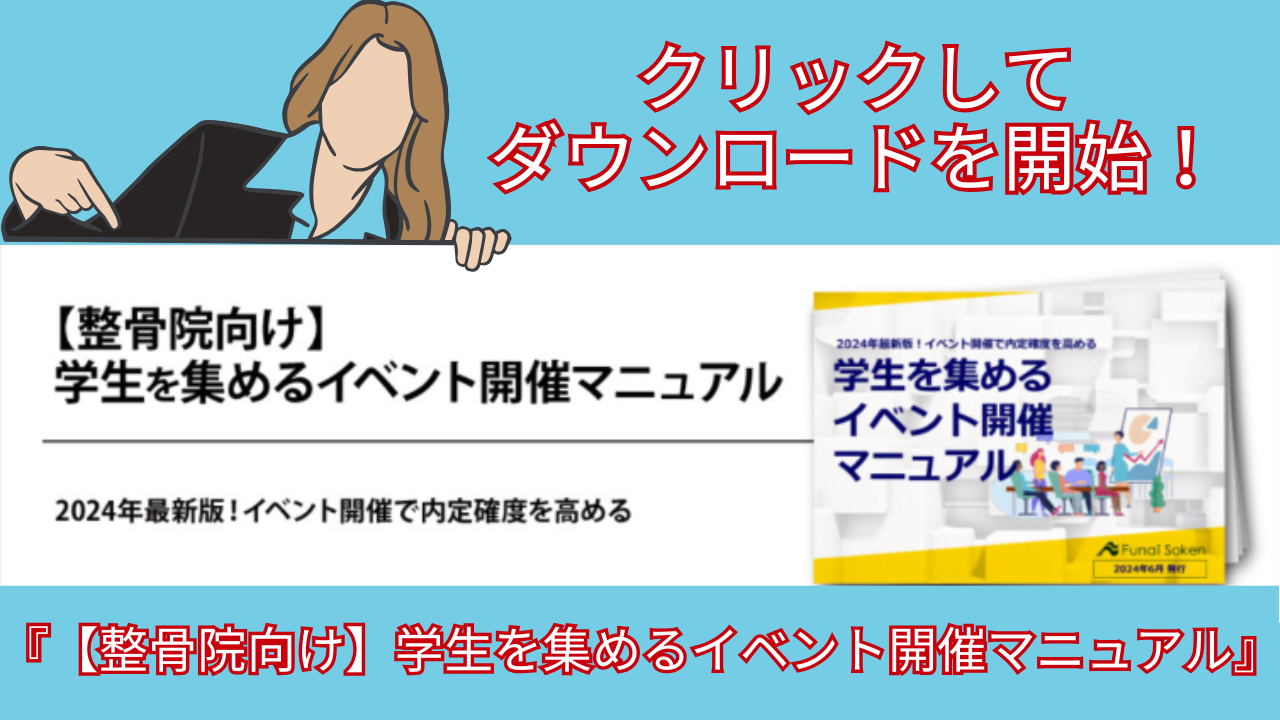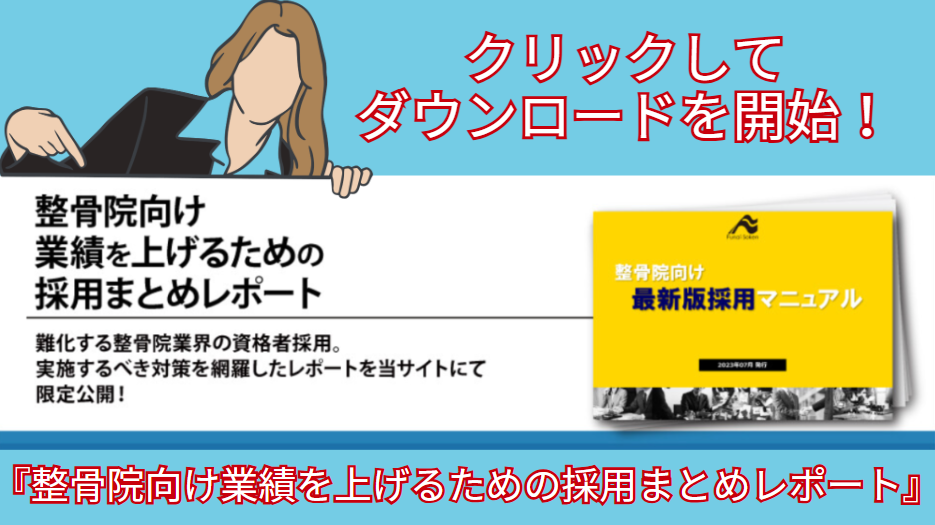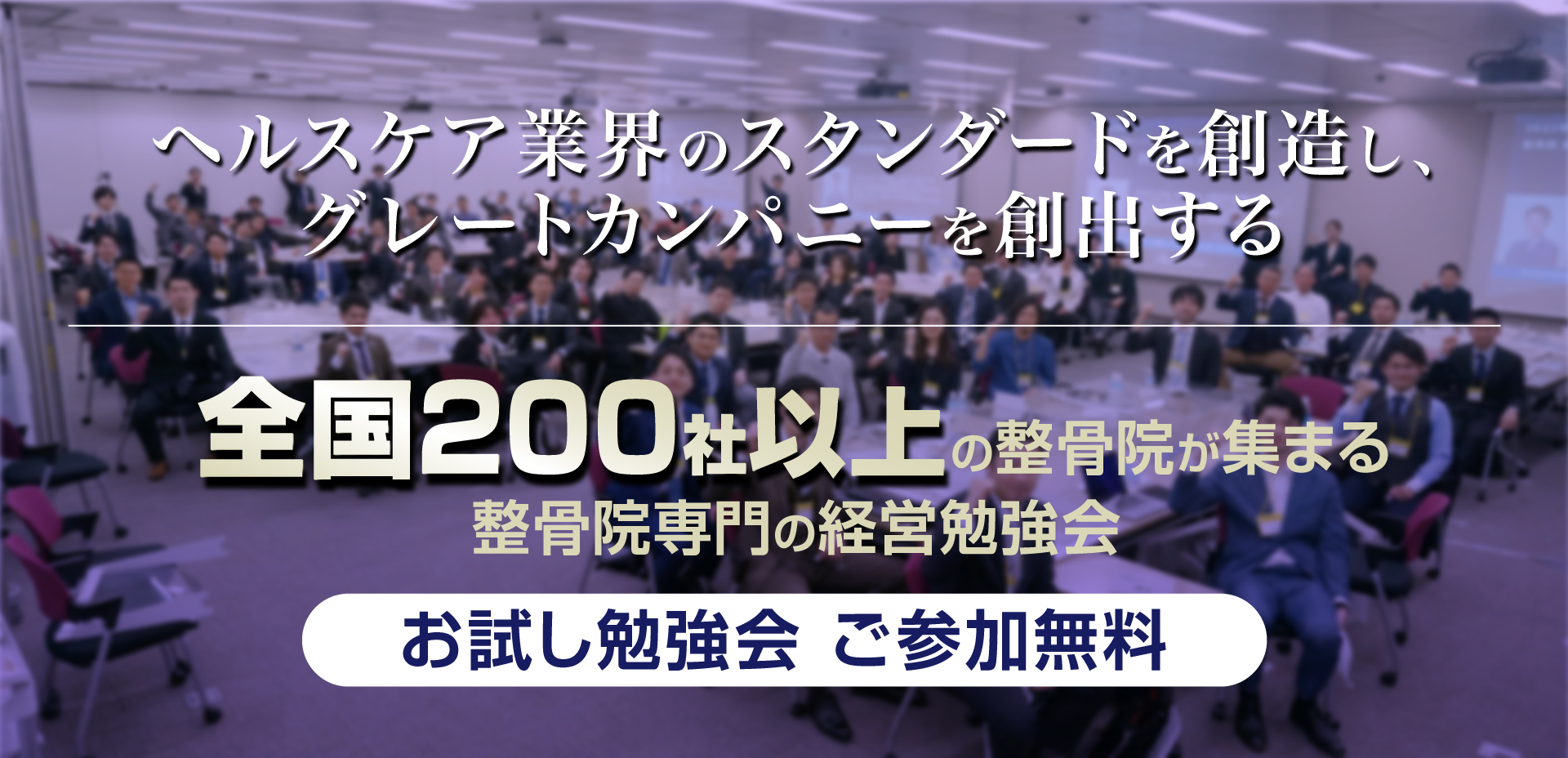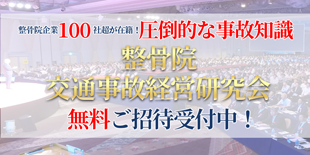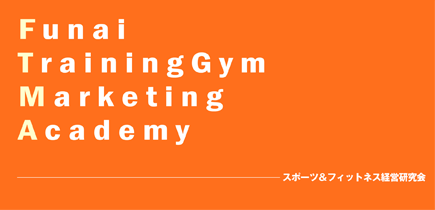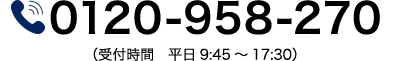Table of Contents
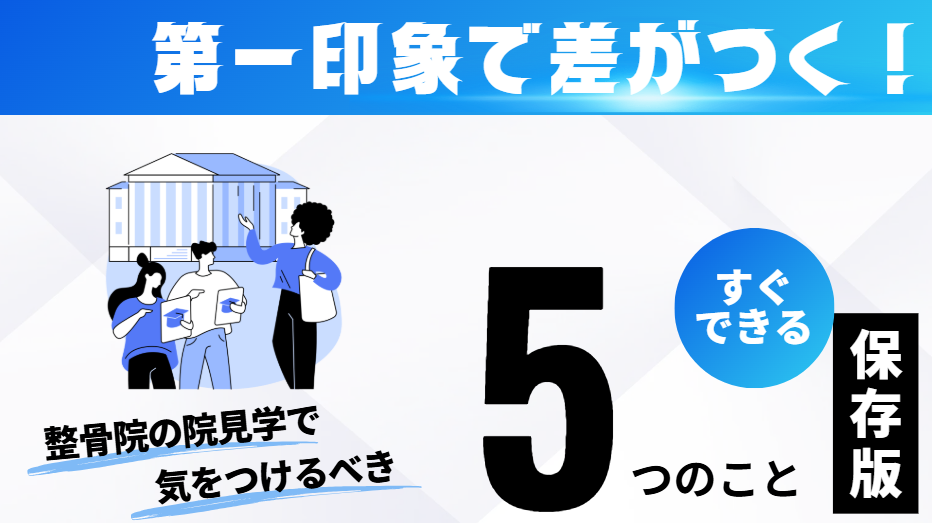
1. この記事はこんな方におすすめ
整骨院経営者の皆様、新卒採用に力を入れていますか?
✓「毎年、採用活動には力を入れているけれど、なかなか優秀な学生が集まらない…」
✓「せっかく採用しても、入社後のミスマッチで早期離職に繋がってしまう…」
✓「院見学に来てくれた学生に、もっと当院の魅力を伝えたい!」
もし、あなたがこのようなお悩みをお持ちなら、この記事はきっとお役に立てるはずです。
柔道整復師の養成校が増え、供給過多が懸念される現代において、採用競争は激しさを増しています。ただ求人広告を出すだけでは、本当に貴院が求める人材と出会うことは難しい時代になりました。これからの時代は「リクルートを制する企業が勝つ」と言われるほど、採用力が企業の成長を左右します。特に新卒採用では、学生が「ここで働きたい!」と強く感じるような「選ばれる理由」を明確に提示することが不可欠です。
その「選ばれる理由」を直接肌で感じてもらう絶好の機会が、「院見学」です。採用活動において、院見学は学生の母集団形成やイベントへの誘導を最大化するための重要なステップであり、採用活動を管理する上での数値管理項目にも含まれています。採用担当者の仕事は、まさにこの母集団の最大化とイベント誘導の最大化にあります。
このコラムでは、学生の心を掴み、貴院のファンになってもらうための院見学の秘訣を、具体的に、そして実践的にご紹介していきます。
貴院の魅力を最大限に引き出し、未来を担う素晴らしい新卒メンバーを迎え入れるためのヒントが満載です。ぜひ最後までお読みいただき、明日からの採用活動に活かしてくださいね!
2. 「選ばれる院」になる!新卒採用における院見学の重要性とは?
なぜ今、「院見学」がこれほどまでに重要なのでしょうか?
その理由を深掘りしていきましょう。
✅新卒採用の現状と院見学の位置づけ
現在、柔道整復師の養成校が増加しており、資格者の供給過多が懸念される中で、採用市場は完全に「売り手市場」となっています。学生は多くの選択肢の中から、自分にとって最適な職場を選ぶことができる立場にあります。このような状況では、単に求人情報を出すだけでは、優秀な人材を獲得することは困難です。これからの時代は「リクルートを制する企業が勝つ」と言われるほど、採用活動の成否が企業の成長を左右します。
その中で「院見学」は、採用活動の極めて重要なステップとなります。これは、学生の母集団形成を最大化し、その後の選考イベント(会社説明会など)への誘導をスムーズに行うための、まさに「入口」とも言える機会なのです。採用担当者の主要な仕事は、この母集団の最大化とイベントへの誘導を最大化することにあります。学生が貴院に興味を持つ最初のきっかけとなる院見学は、その後の選考プロセス全体を左右すると言っても過言ではありません。
✅ミスマッチ防止の第一歩
就職活動中の学生は、単に条件の良い職場を探しているだけではありません。彼らは「自分が本当にここで働くイメージを持てるか」「この職場で成長できるか」「人間関係はどうか」といった、より本質的な部分を知りたいと願っています。院見学は、まさにこれらの疑問に答える最高の機会です。
多くの整骨院経営者様が経験されているかもしれませんが、採用の失敗は、教育で取り返すことが非常に難しいものです。入社後に「思っていたのと違った…」というミスマッチが生じると、早期離職に繋がり、組織の純度が低下してしまうリスクがあります。これは、せっかくかけた採用コストや教育コストが無駄になるだけでなく、既存スタッフのモチベーションにも影響を与えかねません。
院見学を通じて、学生は実際の院の雰囲気、スタッフの働き方、患者様との関わり方、そして院の理念やビジョンを肌で感じることができます。
例えば、株式会社Limitlessでは、経営コンセプトとして「スタッフが成長しながら笑顔で長く働ける会社」を掲げており、この想いを院見学の段階から伝えることで、学生の共感を深めることができます。このような体験は、入社後のギャップを減らし、長く貢献してくれる人材との出会いを促す「理念共感型採用」を実現するための第一歩となるのです。
✅「生理的に無理!」を回避する最初の砦
人間は、情報を視覚、聴覚、体感覚といった感覚を通して受け取ります。特に「第一印象」は、その後の関係性に大きな影響を与えます。心理学では、人の印象が短時間で決まり、その印象がその後の評価を左右すると言われています。
学生が院の門をくぐったその瞬間から、彼らは院の「空気」を感じ取ります。院内の清潔感、整理整頓されているか、スタッフの身だしなみ、挨拶の明るさ、声のトーン、表情…これら全てが学生の「生理的な感覚」に訴えかけます。例えば、「迎え入れるスタッフは患者様を任せる時や紹介するときは必ずティーアップする」とあるように、スタッフ一人ひとりの振る舞いが院全体の印象を形成します。
もしこの第一印象で「生理的に無理」と感じさせてしまえば、どんなに素晴らしい治療技術や福利厚生があっても、その学生は貴院を選ぶことはないでしょう。逆に、ここで好印象を与えることができれば、学生は貴院に対してポジティブなイメージを抱き、より深く知りたいという意欲を持つようになります。これは、貴院の「ファン」を増やすことにも繋がります。
このように、院見学は単なる情報提供の場ではなく、学生の心に「この院で働きたい!」という強い感情を呼び起こすための、極めて戦略的で感情的なアプローチの機会なのです。
3. 対策を取らないとどうなる?放置リスクと現実的な課題
「院見学」の重要性はご理解いただけたかと思いますが、では、もしこの重要な機会への対策を怠ってしまったら、一体どうなってしまうのでしょうか?ここでは、目を背けたくなるような、しかし避けては通れない現実的なリスクと課題についてお話しします。
✅採用難の深刻化:競合に埋もれ、母集団形成が困難に
先ほども触れましたが、現在の採用市場は柔道整復師の養成校が増加していることもあり、完全に「売り手市場」です。学生は多くの選択肢の中から、自分にとって魅力的な院を選びます。もし貴院が院見学の体制を整えず、学生に「選ばれる理由」を提供できなければ、どうなるでしょうか?
残念ながら、学生の目に留まることもなく、貴院の求人は競合の情報の海に埋もれてしまいます。採用活動において、学生の母集団形成は極めて重要です。学校訪問や採用サイト、SNS活用など、多様なアプローチで母集団を最大化し、自社イベントへ誘導することが、採用担当者の主要な仕事だとされています。しかし、院見学という「入口」でつまずけば、その後の選考イベントへ誘導すること自体が困難になります。
さらに、近年では競合院が増加し、1人あたりの集客コストが高騰する傾向にあります。これは採用活動にもそのまま当てはまります。学生が求めているのは、給与や福利厚生といった条件面だけではありません。仕事内容、院の理念や価値観、具体的な働き方、キャリアパス、職場の雰囲気など、多岐にわたる情報を重視しています。これらを院見学で適切に伝えられなければ、せっかく広告費をかけても、優秀な人材との接点すら持てなくなってしまうでしょう。採用計画の立案や、採用活動管理シート・母集団管理シートによる数値管理は必須ですが、まず「見てもらう」段階で足踏みしてしまいます。
✅早期離職のリスク増大:ミスマッチと組織の純度低下
入社後のギャップは、早期離職に直結します。特に、中途採用を「即戦力」として安易に捉え、院の理念や文化との共感を重視しない「即戦力採用」に走ると、組織の純度が低下し、結果的に早期離職を招くリスクが高まります。実際に、期の前半に中途採用者が一気に3人退職したという失敗事例も報告されています。
早期離職は、単に採用・教育にかけたコストが無駄になるだけではありません。残された既存スタッフのモチベーション低下にも繋がり、チーム全体の士気や生産性にも悪影響を及ぼします。これは、組織の「純度」が薄まることに他なりません。
貴院の理念やビジョンに共感し、長く貢献してくれる人材を育てるためには、入社前の段階で「個人のビジョン」と「会社のビジョン」が重なる「共感領域」を創出することが不可欠です。この「共感領域」が大きければ、個人の努力が会社のためになり、会社の努力が自分のためにもなるため、貢献実感が満たされてモチベーションが保たれます。院見学でこの共感を生み出せなければ、早期離職の悪循環に陥ってしまう可能性が高いのです。また、給与や労働環境といった「衛生要因」が満たされても、積極的な満足に繋がるのは「ミッション」や「達成、承認、成長、貢献」といった「動機付け要因」であることも忘れてはなりません。
✅院のブランドイメージ低下:悪い口コミが広がる可能性
一度、採用でミスマッチが生じ、早期離職者が出てしまうと、その情報は良くも悪くも広がりやすくなります。特にSNSが普及した現代では、ネガティブな情報は瞬く間に拡散されるリスクがあります。
学生が「この院はなんか違うな」「話と違う」と感じた場合、それが学校内で広まったり、インターネット上の就職活動掲示板やSNSで共有されたりする可能性があります。悪い口コミや評判は、貴院のブランドイメージを著しく低下させ、今後の採用活動にも大きな影を落とします。
Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)の口コミは、店舗の信頼度や来訪意思決定、さらには検索評価にまで直接影響を与えることが示されています。低評価の口コミは品質向上の貴重なフィードバックとなり得ますが、ユーザーは良い印象よりも悪印象を感じた際に口コミを書きやすい傾向にあります。星評価の総数や分布のバランスも重要であり、信頼性を高めるためにはある程度の評価数が必要とされます。
口コミへの返信をMEO対策の観点から「地域名」「屋号」「症状名」を入れて行うことも重要ですが、そもそものネガティブな印象を与えないことが最優先です。貴院の「顔」とも言える院見学で悪い印象を与えてしまうことは、将来的な集患にも悪影響を及ぼしかねない、非常に危険なリスクなのです。
✅教育コストの無駄:時間と費用の損失
新卒採用は、育成パッケージが整っていなければ、多大な教育コストがかかる可能性があります。もし院見学で貴院の教育体制やキャリアパスを明確に伝えられなければ、入社後に学生は不安を感じ、期待通りの成長が見込めないかもしれません。
「治療が出来て半人前、教育が出来て一人前」という言葉があるように、スタッフの成長には院側の育成努力が不可欠です。この考え方に基づき、「恩送り」として後輩教育を促すこともできます。しかし、教育者不足、教育・マネジメントの属人化、技術の統一不足といった問題があると、せっかく採用した新人が十分に育たず、時間と費用が無駄になってしまいます。新人研修終了後の仮配属期間や、クラス別勉強会、技術勉強会、事故勉強会、栄養勉強会、お金の勉強会、エース研修など、多岐にわたる教育プログラムは、形だけあっても実際に機能していなければ意味がありません。特に未経験者育成のためには、研修動画などナレッジ共有ツールの活用や、詳細なカリキュラム設定が有効とされています。
また、治療コンセプトが全スタッフ間で共有され、細部まで徹底的にこだわられていなければ、患者様への対応にもばらつきが生じ、結果としてスタッフの成長も阻害されます。これは、採用から育成まで一貫した投資が、期待する成果に結びつかないという、経営上の大きな損失となります。
▼無料相談(60分・オンライン/対面)を予約する▼
4. まず取り組みたい!院見学で好印象を与える5つの基本対策
院見学は、貴院の雰囲気や仕事内容、スタッフの様子を肌で感じてもらうための大切なステップです。見学者に「ここだ!」と感じてもらうために、以下の5つの対策を実践してみましょう。
対策1:最高の第一印象を演出するお出迎え
見学者の第一印象は、その後の印象を大きく左右します。温かく、プロフェッショナルなお出迎えを心がけましょう。
- 明るい挨拶と感謝の言葉: 来院された見学者には、まず明るい声で「本日は遠いところ、わざわざお越しいただきありがとうございます!」と、感謝の気持ちを込めてお迎えしましょう。雨の日であれば「雨の中わざわざお越しいただきありがとうございます。お足元濡れてませんか?もし良かったらこちらのタオルをどうぞ」といった、細やかな気遣いが伝わる言葉がけも効果的です。
- 清潔感のある院内とスタッフの身だしなみ: 院内は常に整理整頓され、清潔感を保つことが重要です。お客様の不快感をなくすための接遇の基本でもあります。また、スタッフ全員が身だしなみを整え、清潔感のあるユニフォームを着用しているか確認しましょう。朝礼で身だしなみチェックを行うなど、日頃からの意識づけが大切ですね。
- 見学者の緊張を解く「共感・ねぎらい」の言葉がけ: 見学者は少なからず緊張しているものです。患者様への「共感・ねぎらい」の言葉がけが不安や緊張を和らげるのに重要であるように、見学者に対しても「お越しいただくまで大変でしたね」といった共感や労いの言葉をかけることで、彼らの緊張をほぐし、リラックスした雰囲気で臨んでもらいましょう。
対策2:院の「顔」となるスタッフによる丁寧な説明
貴院の魅力や強みを、院の「顔」となるスタッフが丁寧に説明することで、見学者の理解と共感を深めます。
- 理念・ビジョンの明確な説明と共感の創出: 貴院がどのような想いで患者様と社会に貢献したいのか、その理念やビジョンを明確に伝えましょう。理念は「会社があるべき土台の考え方」であり、「人・企業・社会の未来を創る」といった企業の存在意義を示すものです。社員が会社のビジョンを共有することは、チームワークや相互支援の基盤となります。面接の場が「価値観をすり合わせる最初の教育の場」であるように、院見学の段階から、貴院のMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を軸とした考え方を共有し、共感を促すことが、将来の定着につながります。
- 治療コンセプトや提供サービスの分かりやすい紹介: 貴院の治療コンセプトは「治療の一貫した考え方」であり、全スタッフが共通認識を持つことが重要です。どのような患者様を、どんな方法で、どれくらいの期間・回数で、どのような状態にするのか、そしてなぜそれが可能なのか、具体的に説明できるようにしておきましょう。専門用語を避け、見学者にイメージが湧くように分かりやすく伝えることが大切です。例えば、動画を活用して症状の説明や美容メニューの紹介を行うことで、スタッフによって説明の質に差が出ず、内容を統一して伝えられます。
- 質疑応答の時間を十分に確保し、学生の疑問に真摯に答える姿勢: 見学者が抱く疑問に真摯に答えることで、信頼関係が構築されます。質問しやすい雰囲気を作り、一方的な説明ではなく、双方向のコミュニケーションを意識しましょう。どんな質問にも誠実に対応することで、貴院の透明性と信頼性をアピールできます。
対策3:働くイメージを具体的に見せる「現場体験」
見学者が実際に働くイメージを持てるよう、具体的な現場の様子を見せることが重要です。
- 実際の施術風景や業務の流れの紹介(可能であれば一部体験): 施術の様子や受付業務、カルテ記入, 朝礼, 振り返り、キャンセル対応など、日々の業務の流れを紹介し、可能であれば簡単な業務を体験してもらいましょう。業務の仕組み化や、患者様の情報を正確に伝えるためのカルテなど、効率化された業務フローを見せるのも良いでしょう。
- スタッフ同士の円滑なコミュニケーションやチームワーク: 良好な人間関係は、働きやすい環境の重要な要素です。スタッフ間の円滑なコミュニケーションやチームワークが良い雰囲気は、見学者に安心感を与え、魅力を感じさせます。社内イベントや定期的な懇親会など、コミュニケーションを活性化させる取り組みを紹介するのも良いでしょう。
- 教育体制やキャリアステップの具体例を提示: 成長できる環境は、学生が企業を選ぶ上で重要な要素です。新人教育を重点的に行っていること、技術勉強会やエース研修、面談体制の整備など、具体的な教育制度を提示しましょう。また、院長やマネージャーへの昇進、機能別マネージャー、社員独立制度など、明確なキャリアパスを示すことで、長期的なキャリア形成をイメージさせることができます。
対策4:見学者との「対話」を深めるコミュニケーション術
見学者との会話を通じて、彼らの「本音」や「知りたいこと」を引き出し、より深い関係性を築きましょう。
- ペーシング、ミラーリング、バックトラッキングの活用: 相手の話し方や状態、感情にペースを合わせる「ペーシング」、相手の動作や感情を鏡のように合わせる「ミラーリング」、相手の言葉を繰り返して理解を示す「バックトラッキング」といった手法を用いることで、見学者との心理的な距離を縮め、ラポール形成(信頼関係の構築)を促します。
- 「何を聞きたいか」を引き出すヒアリング力: 見学者の顕在的なニーズだけでなく、彼らが気づいていない「潜在ニーズ(本音)」、つまり本当に知りたいことや不安に思っていることを引き出すヒアリング力が重要です。オープンクエスチョンを積極的に使い、見学者が自由に話せる雰囲気を作りましょう。
- 一方的な説明ではなく、双方向のコミュニケーションを意識: 一方的に情報を与えるのではなく、見学者からの質問や意見を促し、対話を通じて理解を深めましょう。見学者の関心事や悩みを整理し、彼らが自ら疑問を解決できるように導く姿勢が大切です。
対策5:見学後も良好な関係を続けるフォローアップ
院見学は終わりではなく、採用活動の一環として継続的な関係構築が重要です。
- 感謝のメッセージと、質問や相談を受け付ける窓口の提示: 見学後には、速やかに感謝のメッセージを送りましょう。そして、見学中に聞けなかったことや、後から出てきた質問、相談を受け付ける窓口を明確に提示することで、見学者とのつながりを維持します。
- 今後の選考プロセスやイベントの明確な案内: 次のステップ(選考プロセス)や、今後開催されるイベント(説明会、インターンなど)について、具体的に案内しましょう。いつ、何を、どのように進めるのかを明確にすることで、見学者の不安を軽減し、貴院への関心を維持させることができます。
- 見学者の情報管理(母集団管理シートの活用): 見学者の情報は、単に採用のためだけでなく、今後のリレーションシップ構築のために重要です。個々の見学者の興味や関心、質問内容などを記録し、次のアプローチに活かせるよう情報管理を行いましょう。患者様のカルテと同様に、情報管理は大切です。
5. よくある質問
院見学に来る学生や求職者が抱きやすい質問について、事前に準備しておくことで、スムーズで質の高い対応が可能になります。
Q1: 院見学時の服装はどのようなものが良いですか?
A1: 基本的には「清潔感のある服装」を心がけましょう。スーツが無難ですが、私服の場合は襟付きのシャツやシンプルなトップスに、きれいなパンツやスカートなど、ビジネスシーンに相応しい清潔感のある服装が良いでしょう。動きやすい靴を選ぶことも大切です。貴院の雰囲気に合わせてカジュアルな指示がある場合はそれに従ってください。
Q2: 見学時にどのような質問をすれば、院の雰囲気をより深く理解できますか?
A2: 院の雰囲気を深く理解するためには、以下のような質問がおすすめです。
「スタッフの皆さんは、どのような時にやりがいを感じますか?」
「教育体制について、具体的にどのようなサポートがありますか?新人はどのようなステップで成長していきますか?」
「スタッフ同士のコミュニケーションで大切にしていることは何ですか?休憩時間や業務外での交流はありますか?」
「貴院の治療コンセプトについて、具体的にどのような想いや考え方がありますか?患者様にはどのように伝えていますか?」
「将来的にどのようなビジョンを描いていますか?その中で、私のような立場の者がどのように貢献できますか?」
これらの質問を通じて、貴院の理念、教育体制, チームワーク、治療への考え方、そして将来性といった、より深い情報を引き出すことができるでしょう。
Q3: 院見学で採用担当者が「これは聞かれたくないな」と思うことはありますか?
A3: 採用担当者が「聞かれたくない」と感じる質問は、主に以下の点に偏ったものです。
・待遇面への偏り: 初めての院見学で、仕事内容や院の理念・雰囲気への関心よりも、給与、休暇、残業時間、福利厚生といった待遇面に終始する質問は、良い印象を与えにくいでしょう。貴院が「時間とお金の交換という働き方を望むのであれば、うちよりも楽なところはいっぱいあるから絶対にそっちに行った方がいいよ」と明確に伝えているように、金銭的な側面ばかりを追求する姿勢は、貴院の求める人材像と乖離する可能性があります。
・受身的な姿勢: 「何をすればいいですか?」といった、指示待ちの姿勢が強く感じられる質問も、主体性や成長意欲が見えにくいため、あまり好ましくありません。 もちろん、待遇は働く上で非常に大切な要素ですが、まずは貴院への興味や貢献意欲を示す質問を優先し、その上で働き方に関する疑問を解消していく姿勢が望ましいでしょう。
Q4: 院見学の際、学生からの突っ込んだ質問にはどう対応すれば良いですか?
A4: 学生からの突っ込んだ質問は、貴院への関心が高い証拠と捉え、誠実に対応することが重要です。
・質問を歓迎する姿勢: まずは「良い質問ですね」「よくぞ聞いてくれました」など、質問を歓迎する言葉で受け止めましょう。
・正直かつ具体的な回答: たとえ答えにくい内容であっても、できる限り正直に、具体的に答えることが信頼につながります。例えば、過去の離職率や課題について聞かれた場合、事実を述べつつ、現在どのように改善に取り組んでいるかを説明することで、貴院の課題解決への真摯な姿勢を示すことができます。
・一方的な説明にならない工夫: 質問の意図を理解し、「なぜそう思うのか?」など、さらに深掘りする問いかけをすることで、学生の考えを引き出し、双方向の対話につなげましょう。
・「知らない」を恐れない: すべての質問に完璧に答える必要はありません。「それは現状ではお答えできませんが、今後検討していきます」といったように、分からないことや現時点で言えないことは正直に伝えましょう。
6. まとめ&新卒採用・院見学で困ったときの相談先
ここまで、院見学で好印象を与えるための具体的な対策と、よくある質問への対応についてお伝えしてきました。
院見学は単なる見せ物ではありません。貴院の魅力と本質を伝える重要な機会です。 見学者が貴院で働く未来を具体的にイメージでき、「ここで働きたい!」と心から思ってもらえるような、最高の体験を提供しましょう。
「知っている」と「できる」は違います
今回ご紹介した内容は、知っているだけでは意味がありません。実際に実践し、その結果から改善を重ねることで、貴院ならではの魅力を最大限に引き出すことができます。うまくいったこと、いかなかったことを振り返り、次に活かすPDCAサイクルを回し続けることが大切です。
新卒採用・院見学で困ったときの相談先
もし、
「具体的な実践方法が分からない」
「今のやり方で本当に良いのか不安」
「もっと効果的な採用戦略を立てたい」
とお悩みの場合は、ぜひ専門家にご相談ください。船井総合研究所では、無料レポートの提供や、経営研究会、月次コンサルティングなどを通じて、整骨院経営者の皆様の採用力強化と組織力向上をサポートしています。
貴院の採用活動が成功し、素晴らしい仲間と出会えることを心から願っています!
▼無料相談(60分・オンライン/対面)を予約する▼
まずは無料個別相談で整骨院経営のお悩みを解決!

弊社の整骨院・接骨院・整体院の経営専門のコンサルタントが、初回のみ無料で個別相談をご対応させて頂きます。
・売上を伸ばしたいが、何から始めればいいのかわからない
・患者様数を増やしたいが、何から始めればいいのかわからない
・採用をしたいが応募が全然こない
・事業拡大に伴い、育成環境や評価制度を整備したい
など、様々な経営のお悩みに対応しております。
是非、無料個別相談をご活用ください。
船井総研ならではの治療院経営の現場最新情報&ノウハウが満載の無料メールマガジン
自費治療で売上が月200万円以上UP!新規交通事故患者が毎月8名以上集まる!
その秘密を無料メルマガで大公開!!