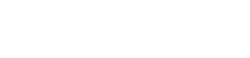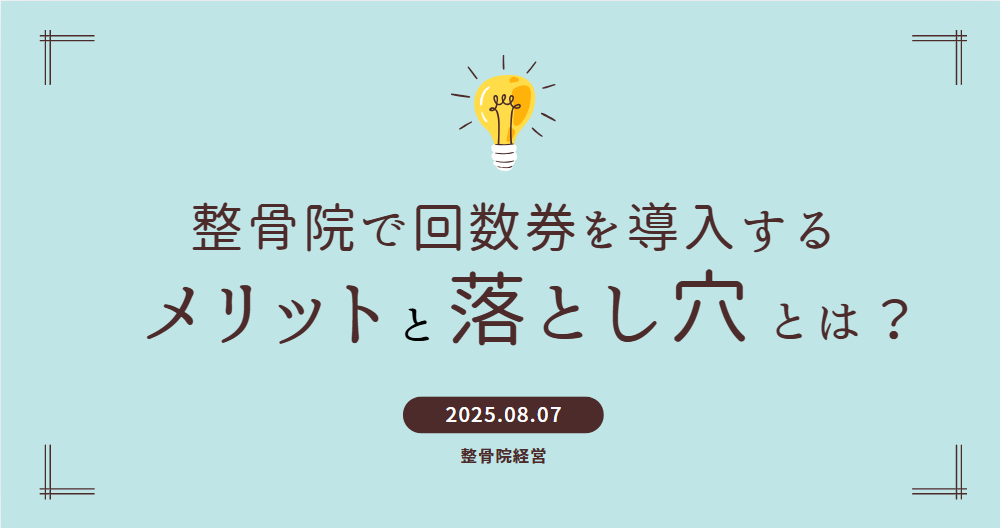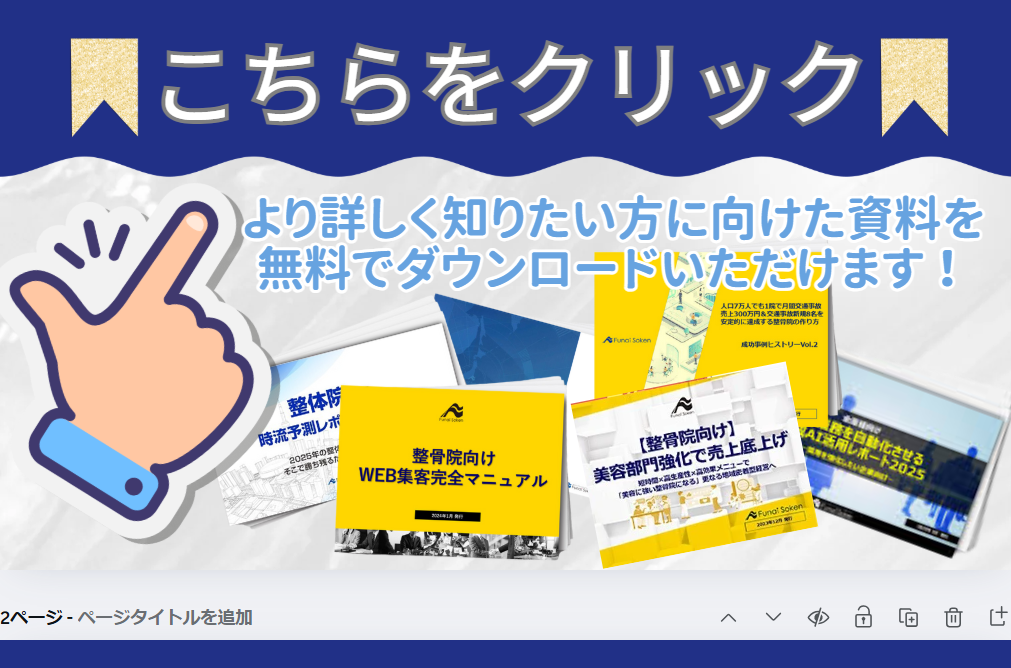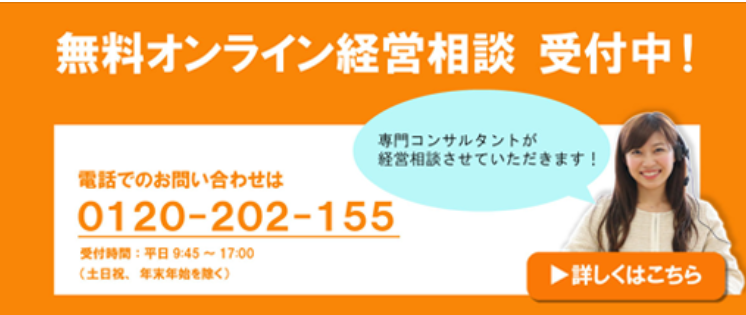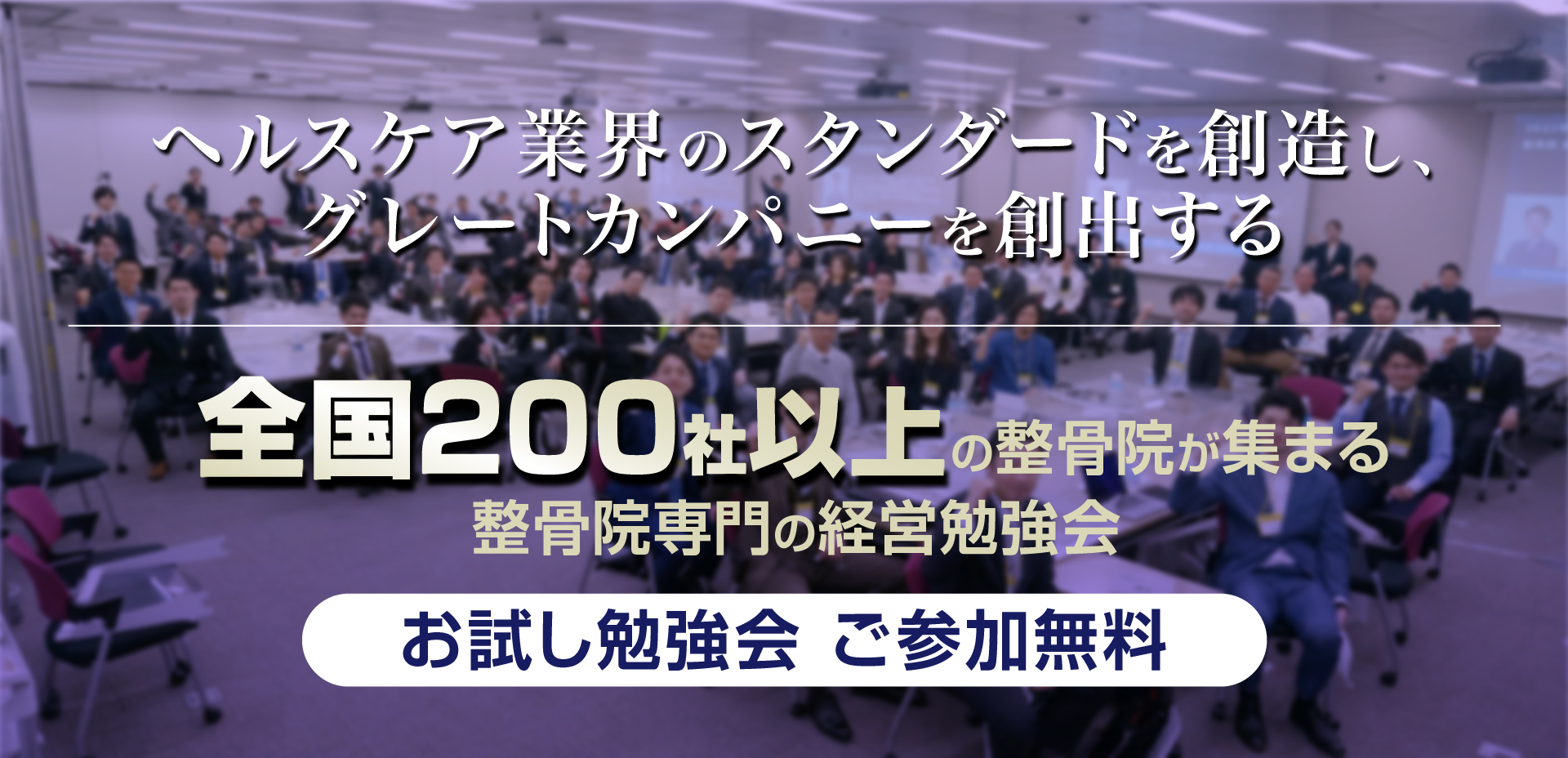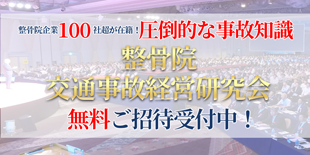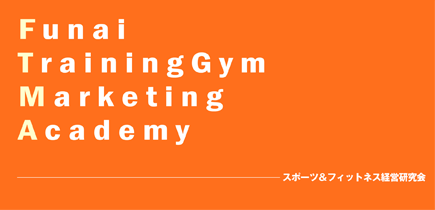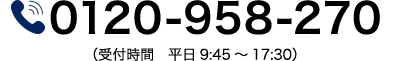Table of Contents
1️⃣この記事はこんな方におすすめ
整骨院経営者の皆さん、日々の業務、本当にお疲れ様です! 突然ですが、あなたの院では、このようなお悩みはありませんか?
- 「新規の患者様は増えているのに、なぜか売上が伸び悩んでいる…」 せっかく来てくださっても、一度きりの来院で終わってしまうケースが多く、頭を抱えている先生はいませんか?
- 「自費メニューを導入したものの、なかなか患者様に継続してもらえない」 最新の治療機器や専門性の高い施術を取り入れたのに、「単発利用で終わり」という状況にモヤモヤしているかもしれませんね。
- 「もっと安定した経営基盤を築きたいが、具体的な一手が打てない」 売上が毎月波があって、将来の投資やスタッフの給与計画が立てにくい、と感じている方もいらっしゃるでしょう。
- 「スタッフの継続提案スキルにばらつきがあり、教育に悩んでいる」 どのスタッフも同じように患者様に治療の必要性を伝え、継続利用に繋げてほしいのに、なかなかうまくいかない、というご相談もよく耳にします。
今日は、多くの整骨院で導入されている「回数券」に焦点を当て、そのメリットを最大限に活かし、落とし穴を避けるための具体的な方法を、専門的な視点と現場のリアルな声も交えながら、分かりやすくお伝えしていきます。
さあ、一緒に「患者様にも、院にも、スタッフにも」良い回数券導入の秘訣を探っていきましょう!
2️⃣回数券とは?
さて、回数券という言葉、普段からお使いの先生も多いと思いますが、改めて「整骨院にとっての回数券」とはどんな存在なのか、その本質に迫ってみましょう。
🔑整骨院における回数券(プリペイドカード)の定義と役割
整骨院における回数券とは、ズバリ「複数回の施術料金を、事前にまとめてお支払いいただく仕組み」のことです。プリペイドカード形式で提供されていることもありますね。患者様にとっては、一括で支払うことで1回あたりの施術単価が割引されるという、経済的なメリットが魅力となります。
では、私たち整骨院側から見た回数券の役割とは何でしょうか? それは、「患者様の継続的な来院を促し、より効果的な治療に繋げるための強力なツール」であるということです。もちろん、事前にまとまった売上が確保できることで、キャッシュフローが安定し、経営計画が立てやすくなるという側面もあります。
🔑継続的な治療を促す仕組みとしての位置づけ
「短期間での通院指導がしやすく、効果を実感していただきやすい」。これが、回数券がもたらす最大のメリットの一つです。
患者様が回数券を購入されるということは、「これから、しっかり治すぞ!」という意識を持ってくださっている証でもあります。私たちはそのお気持ちに応えるべく、治療計画に沿った適切な頻度での来院を促すことができます。これにより、単発の施術ではなかなか得られない、症状の「根本改善」へと導きやすくなるのです。
例えば、ぎっくり腰や寝違えといった急性期の痛みは、数回の施術で劇的に改善することもあります。しかし、その痛みがどこから来ているのか、なぜ繰り返してしまうのか、といった根本原因にアプローチするには、ある程度の期間と回数が必要になることが多いですよね。回数券は、そうした「継続的なケア」への橋渡し役を担ってくれるわけです。
🔑都度払い、サブスクリプションモデルとの違い
ここで、よく比較される「都度払い」や、最近注目を集めている「サブスクリプションモデル」との違いも見ていきましょう。
- 都度払いとの違い: 都度払いは、文字通り患者様が来院されるたびに料金をお支払いいただく形式です。患者様は「行きたい時にだけ行く」という気軽さがありますが、その反面、症状が少し良くなると、どうしても「もう大丈夫かな?」と来院が途絶えてしまう傾向があります。回数券は、先にまとめてお支払いいただいている分、「せっかく買ったんだから、ちゃんと通って元を取ろう」という心理が働きやすく、通院のモチベーション維持に繋がりやすいのが大きな違いです。
- サブスクリプションモデルとの違い: サブスクリプション(月額定額制や通い放題など)は、回数券とは異なり、期間内であれば何度でも利用できる「サービスの利用権」を提供するモデルです。 サブスクのメリットとしては、院のキャッシュフローが非常に安定する、患者様が「健康維持」のために気軽に継続利用できる、スタッフの「リピートさせなければ」という心理的ストレスが軽減される、といった点が挙げられます。 一方、回数券はあくまで「回数」が限定されています。株式会社メディカルホスピタリティの事例では、最初からサブスク(会員制)を提案すると、患者様にとってもスタッフにとってもハードルが高いため、まず「プリカ(回数券)で通う間に患者様との関係性を構築し、患者教育を行う」という段階を踏んでいるとされています。
つまり、回数券は「都度払い」から「サブスクリプション」へと患者様の継続意識を高めていく上で、非常に有効な「中間ステップ」としても機能するのです。また、回数券は「一度でまとまった売上を確保できるため、生産性を上げやすく、予算の埋め合わせが可能」というメリットもあります。
このように、回数券は単なる割引販売ではなく、患者様の健康意識を高め、治療効果を最大化し、さらには院の安定経営に貢献する、多角的なメリットを持つビジネスモデルと言えるでしょう。
3️⃣対策を取らないとどうなる?放置リスクと現実的な課題
「回数券、うちにはまだ早いかな」「今のままでも、なんとなく回ってるし」—そう思っている先生もいらっしゃるかもしれませんね。しかし、回数券導入をはじめとする継続的な施策を講じない場合、知らず知らずのうちに、様々な「落とし穴」にはまってしまう可能性があります。
ここでは、その具体的なリスクと、多くの整骨院が直面している現実的な課題を、3つの視点からお伝えします。
⚠️患者様が「通い続けられない」深い理由
まず一番に直面するのが、患者様が「単発的な来院で終わってしまう」という問題です。これは、単に患者様が飽きてしまう、という表面的な理由だけではありません。深く掘り下げると、そこにはいくつか根本的な原因が潜んでいます。
❌痛みが取れたら来なくなる心理
多くの患者様は「痛みを取りたい」という顕在的なニーズを持って来院されますね。そして、施術によって痛みが和らぐと、「もう大丈夫」と感じて来院が途絶えてしまうことが多々あります。これは、患者様にとって痛みの解消が「ゴール」であると認識されているためです。しかし、私たちプロの視点から見れば、痛みが取れたとしても、その根本原因が解決されていない限り、再発のリスクは常につきまといます。回数券がないと、この「根本改善」や「健康維持」の重要性を伝えきれず、患者様自身の健康寿命を延ばす機会を逸してしまうことにもなりかねません。
❌治療の必要性が「腑に落ちて」いない現状
患者様が継続して通院しないもう一つの大きな理由は、「なぜ、この治療を継続する必要があるのか」が患者様自身に明確に伝わっていない、ということです。私たちがどれだけ専門的な知識や技術を持っていても、それを患者様が「素人でも理解できる基準」で納得できる形で伝えなければ、行動には繋がりません。 例えば、「今は痛みが引いても、骨盤の歪みが残っていると、将来的にまた同じ症状が出やすくなりますよ」と伝えても、患者様は漠然とした不安しか感じません。「具体的にどうなるの?」「私の体はどうなっているの?」といった疑問に対し、視覚や体感を伴う説明(鏡や写真を使った歪みの可視化、触診による圧痛の確認など)ができていないと、彼らは治療の必要性を「自分事」として捉えられないのです。結果として、患者様は「とりあえず痛みが引いたから、まあいいか」と、通院を中断してしまいます。
❌都度払いの「気軽さ」が継続を阻害する側面
都度払いは患者様にとって手軽である反面、「いつでも来られる」という気軽さが、かえって「また今度でいいか」という先延ばしに繋がりやすいという側面があります。回数券のように、ある程度の期間や回数をコミットする形がなければ、患者様は痛みが少し和らいだり、忙しくなったりすると、優先順位を下げてしまう傾向があるのです。
⚠️経営の不安定化を招く「見えないリスク」
患者様の離反は、そのまま経営の不安定化に直結します。これは、日々の売上にダイレクトに響くだけでなく、経営の未来を見通しにくくする「見えないリスク」を抱えることになります。
❌売上予測の難しさと資金繰り
都度払いの患者様が多いと、月ごとの売上が読みにくくなります。新規患者様の獲得数に左右されやすいため、経営計画や予算設定が難しくなるでしょう。まとまった売上が事前に確保できないと、新たな設備投資やスタッフの増員、教育など、未来に向けた投資に踏み切りにくくなるという課題も生まれます。
❌新規集患に偏ったコスト増
既存患者様のリピートが安定しないと、常に新規患者様を追い求めなければなりません。新規集患には、広告費や宣伝費、WEB対策費用など、多大なコストがかかります。エキテンのようなオンラインプラットフォームでの口コミ集めや上位表示、プロカメラマンによる写真撮影、紹介文の充実なども、継続的な取り組みが必要です。リピート率が低いままでは、せっかく集めた新規患者様も定着せず、まるで「ザルのような経営」になってしまいます。これは、いくら水を注いでも底から漏れていくようなもので、非常に非効率的です。
❌スタッフのモチベーション維持の難しさ
患者様が継続しないと、スタッフのモチベーションにも影響が出ます。「せっかく一生懸命治療したのに、また来院してくれない…」「患者様に必要性が伝わらない」といった経験は、スタッフのやりがいを削ぎます。継続的な治療計画や回数券の提案に苦手意識を持つスタッフがいる場合、さらにこの問題は深刻化します。スタッフが自信を持って継続治療を提案できない、あるいはそのための教育体制が不十分だと、結果として売上にも繋がりません。会社として「人財教育」に力を入れ、スタッフ一人ひとりの可能性を引き出す環境を整えることが重要です。
⚠️激化する競争環境と「時間売り」の限界
最後に、整骨院業界全体を取り巻く厳しい環境についても触れておきましょう。
❌競合増加と市場の飽和
ヘルスケア産業の市場は拡大傾向にありますが、同時に整骨院の数も増え、競争は激化の一途を辿っています。特に都市部では、リラクゼーション、ヘッドスパ、慢性系整体、姿勢改善、難治専門、女性専門、フェムケア、巻き爪など、様々な専門業態が登場し、市場の細分化が進んでいます。このような「成熟期」においては、単に「施術が上手い」「先生がいい」だけでは、他院との差別化が難しくなってきています。
❌「時間売り」モデルの収益性の限界
多くの整骨院が提供する「〇分〇円」といった、時間や単発の施術に依存する「時間売り」モデルは、収益性の限界に直面しています。生産性を高めるためには、より多くの患者様を短い時間で施術するか、単価を上げるしかありませんが、それには限界があります。 サブスクリプションモデルが注目される理由の一つも、従来の「時間売り」モデルの生産性の低さを補う点にあります。回数券は、この「時間売り」から一歩進んだ、安定的な収益確保のための有効な手段と言えるでしょう。
❌自費治療・予防メニューへの移行の遅れ
保険診療の適応が厳しくなり(療養費の適正化)、保険売上に依存していた整骨院は経営が成り立たなくなってきています。このような時流の中で、高効果な自費治療や、根本改善、健康増進、予防といった継続的なケアの提供が不可欠となっています。しかし、自費メニューへの移行が遅れると、患者様の「とにかく痛みを取りたい」というニーズから一歩踏み込んだ「健康であり続けたい」という潜在ニーズを捉えきれず、結果として時代の流れから取り残されてしまうリスクがあるのです。
これらのリスクと課題を放置することは、売上の伸び悩みだけでなく、スタッフの疲弊、そして院の持続的な成長を阻害する大きな要因となります。だからこそ、回数券の導入は、単なる売上アップ策に留まらない、未来を見据えた重要な経営戦略なのです。
4️⃣まず取り組みたい基本的な回数券導入対策
パート3で、回数券導入を怠ることで生じる様々なリスクについてお話ししました。患者様の継続率の低下、経営の不安定化、そして激化する業界の競争—これらは、日々の経営に大きな影を落とします。
では、これらの課題を乗り越え、院を安定成長させるためにはどうすれば良いのでしょうか? 答えの一つが、回数券の戦略的な導入と運用です。ここでは、回数券導入の「土台」を固めることから、患者様への伝え方、そしてスタッフの育成まで、実践的なステップを具体的に解説していきます。
⭐回数券導入の「土台」を固める
回数券を単なる「割引チケット」として導入するだけでは、その真価は発揮されません。まずは、その導入目的を明確にし、院全体の治療コンセプトと連動させることが重要です。
⭕なぜ回数券を導入するのか?目的を明確に
回数券は、患者様の「継続」を促すための有効な手段です。継続してもらうことで、患者様は根本的な改善や健康維持へと繋がり、私たちは安定した売上を確保できます。つまり、回数券は「患者様の健康寿命を延ばす」という私たちの理念を実現するためのツールであり、同時に「院の安定経営」という目標を達成するための戦略でもあるのです。この二つの目的を明確にすることで、導入に対するスタッフの理解も深まります。
⭕治療コンセプトとの連動性を高める
あなたの院が「どのような患者様に」「どのような方法で」「どれくらいの期間・回数で」「どのような状態になってほしいのか」。この「治療コンセプト」を明確にすることが、回数券設計の出発点です。そして、このコンセプトを全スタッフが共有し、一言一句間違えずに言える状態を目指しましょう。
例えば、「慢性的な腰痛に悩む方に、3ヶ月間で痛みのない生活を取り戻してもらい、再発予防のためのセルフケアも習得させる」というコンセプトであれば、それに合わせた回数や期間を設定した回数券を用意します。痛みだけを取り除く「卒業型」の治療コンセプトでは、回数券導入の難易度が上がりますので注意が必要です。
⭕回数券の「設計」のポイント
回数券の設計では、患者様が「通い続けやすい」と感じる価格と期間を設定することが大切です。
- 期間と回数: 治療コンセプトに沿って、「改善期」「安定期」「メンテナンス期」など、段階的な通院計画に合わせた回数券を用意すると、患者様もイメージしやすくなります。
- 価格: 都度払いの単価と回数券の単価を比較して、回数券がお得であることを明確に示しましょう。高すぎるとハードルが高く、成約に繋がりません。電子決済の導入も、患者様の購入ハードルを下げる上で有効です。
⭐患者様が「納得して継続」する仕組みづくり
回数券を導入しても、患者様がその価値を理解し、納得して購入してくれなければ意味がありません。ここでは、患者様とのコミュニケーションの質を高めることに焦点を当てます。
⭕患者様の「真のニーズ」と「ゴール」を共有する
患者様が来院する一番の理由は「痛みを取りたい」ということが多いですが、私たちはそのさらに奥にある「なぜ、痛みを取りたいのか」「痛みがなくなったら何をしたいのか」という「真のニーズ」に寄り添う必要があります。例えば、「痛みがなくなったら、趣味のゴルフを再開したい」「孫と公園で思いっきり遊びたい」といった具体的なゴールを引き出すことで、患者様は治療の必要性を「自分事」として捉え、継続へのモチベーションが高まります。
問診時には、「はい」「いいえ」で答えられる質問だけでなく、患者様が自由に話せる質問を投げかけ、日常の状況を丁寧に聞き出すことで、より深い関係性を築けます。
⭕「プロ」としての説明と「価値の可視化」
患者様に継続の必要性を理解してもらうためには、私たちの専門的な知識を「分かりやすい言葉」で伝えることが不可欠です。
- 視覚・体感を使った説明: 鏡や写真を使って身体の歪みを可視化したり、触診で圧痛を確認してもらったりと、患者様自身が自分の身体の状態を「見て」「触って」「実感」できるように工夫しましょう。左右差や可動域の角度など、具体的な数字を比較対象として使うと、より分かりやすくなります。
- 紙芝居ツールの活用: 治療コンセプトや治療内容、なぜこの治療が必要なのかを、図やイラストを使った「紙芝居ツール」で説明すると、専門知識がない患者様でも理解しやすくなります。
- プレ施術とBefore&After: 初回時に簡単なプレ施術を行い、その場で痛みの変化や身体の軽さを実感してもらうことで、「この治療なら良くなる」という信頼感を勝ち取れます。施術中に「先ほど〇〇だったのが、△△のようになりました」と積極的に声かけし、変化を言語化して伝えましょう。
- 治療計画の明確化: 身体のプロとして、最適な通院ペースや治療の全体像を明確に提示し、患者様のライフスタイルに合わせて短期的な目標を設定する「譲歩」も大切です。
⭕「お得感」と「安心感」で後押しするクロージング
回数券の提案は、患者様が継続を決断する最後のステップです。
- お得度の可視化: 都度払いとの比較など、「回数券がいかにお得か」を視覚的に分かりやすく提示するツールを活用しましょう。
- ダブルバインド: 患者様に「どちらの回数券にしますか?」といった、選択肢をこちらから提示し、患者様自身に「決断」してもらう「ダブルバインド」という手法も有効です。ただし、あくまで患者様の選択を尊重するスタンスが重要です。
- 無理強いはしない: 押し売りのような印象を与えないよう、患者様のニーズと真摯に向き合う姿勢を忘れてはいけません。
⭐スタッフが「自信を持って提案」できる教育体制
どんなに素晴らしい回数券の仕組みを作っても、現場で患者様に提案するスタッフが自信を持てなければ、その効果は半減してしまいます。スタッフの教育とマニュアル化は、回数券導入成功の鍵を握ります。
⭕「落とし込み」重視のスタッフ教育
「ビジネスモデルを組むこと以上にスタッフへの落とし込みが重要」という言葉があるように、スタッフが回数券の目的や価値を深く理解し、自信を持って提案できるようになることが大切です。
- 治療コンセプトの共有: まずは院の治療コンセプトをスタッフ全員に徹底的に理解させ、患者様への来院プログラムを明確にします。
- マニュアルとロールプレイング: 初診から回数券提案、その後の継続までの流れを詳細なマニュアルとして整備し、ロールプレイングを繰り返し行うことで、どのスタッフでも同じ品質の対応ができるようにします。マニュアルは、施術に集中できる、コミュニケーションに集中できる、教え漏れを防ぐ、院長の教育負担を減らすなど、多くのメリットがあります。
- 「ケースストック」「準備」「振り返り」のサイクル: 新規患者様の対応に際して、「ケースストック(症例分析)」「準備(シミュレーション)」「振り返り(反省と改善)」の3つのステップを必ず行う体制を作りましょう。これにより、スタッフは経験値を積み重ね、同じ失敗を繰り返さずに成長できます。特に、振り返りシートでは、自身の対応を言語化し、上長とのすり合わせを通じて具体的な改善点を明確にすることが重要です。
⭕モチベーションを高める「仕組み」と「環境」
スタッフがやりがいを感じ、主体的に回数券提案に取り組める環境づくりも重要です。
- 理念浸透と目標共有: 院の理念や目標をスタッフ全員で共有し、それぞれの業務が患者様の健康、ひいては社会貢献に繋がっていることを実感できる機会を増やしましょう。
- 達成感と承認: 回数券販売の目標達成を評価し、個々の努力や成果を認め、賞賛することで、スタッフのモチベーションは向上します。
- 継続的な教育投資: マネージャー育成をはじめとする人材育成に投資し、スタッフが自身の成長を感じられる機会を提供することは、定着率向上にも繋がります。教育は「感謝の連鎖」であり、自分が受けた教育を後輩に施すことで、組織全体のレベルアップが図れます。
回数券の導入は、一時的な売上アップだけでなく、患者様との長期的な信頼関係を築き、スタッフの成長を促し、院の持続的な発展を可能にするための重要な戦略です。ぜひ、今日から一歩踏み出してみてください。
5️⃣よくある質問
回数券の導入は、患者様にとっても、そして院にとっても大きなメリットをもたらす可能性がありますが、同時に様々な疑問や不安が湧いてくることも自然なことです。ここでは、皆さまからよく寄せられる質問にお答えし、回数券導入への不安を解消していきます。
Q1. 回数券を導入したら、患者さんが離れてしまうのではないかと心配です。
このご心配、よくわかります。患者様が「回数券を売りつけられた」と感じてしまっては、本末転倒ですよね。しかし、回数券は適切に導入・運用すれば、むしろ患者様との関係性を深め、継続率を高める強力なツールになります。
大切なのは、「割引」だけを前面に出すのではなく、患者様にとっての「価値」を明確に伝えることです。
- 患者様の真のニーズとゴールを共有する: 患者様が「なぜ、痛みを取りたいのか」「痛みがなくなったら何をしたいのか」といった深いニーズを引き出し、その「ゴール」を達成するために、どれくらいの期間、どのような治療が必要なのかを丁寧に説明しましょう。回数券は、そのゴールへ向かうための最適な「計画」であり「手段」であることを伝えるのです。
- 治療の必要性と変化を「見える化」する: 鏡や写真で体の歪みを視覚化したり、施術前後の変化を患者様自身に体感してもらったり(プレ施術も有効です)。具体的な数字(可動域の改善度など)を用いると、さらに説得力が増します。
- 「納得」を最優先にする: 決して無理強いはせず、患者様が回数券の価値を理解し、「自ら継続したい」と納得して購入できるよう、選択肢を提示する「ダブルバインド」などのコミュニケーション手法も有効です。
回数券は患者様の健康維持・増進をサポートするための「通院計画」であり、その計画を円滑に進めるための「お得な選択肢」である、というメッセージが伝われば、患者様は安心して継続してくださるでしょう。
Q2. 回数券の価格設定や期間設定はどのように考えれば良いですか?
回数券の価格や期間設定は、院の治療コンセプトと深く結びつけることが重要です。
- 治療コンセプトに基づく設計: あなたの院が「どのような患者様に」「どのような治療を提供し」「どれくらいの期間・回数で」「どのような状態になってほしいのか」という治療コンセプトを明確にしましょう。このゴールに到達するために必要な総回数を算出し、それに合わせた回数券(例:改善期用、メンテナンス期用など)を設定します。
- お得感の明確化: 都度払いの料金と比較して、回数券がいかにお得であるかを分かりやすく提示することが大切です。ただし、安売りしすぎると院のブランド価値を損ねる可能性もあるため、バランスを見極めましょう。
- 通いやすさと継続性の両立: 患者様が「通い続けやすい」と感じる価格帯と、治療効果を最大限に引き出すための頻度・期間を考慮して設定します。例えば、「1ヶ月で集中的に改善を目指す〇回券」「3ヶ月で体質改善を目指す〇回券」のように、期間と目標を明確にすると良いでしょう。
- 電子決済の導入:回数券の購入ハードルを下げるために、クレジットカードなどの電子決済を導入することも有効です。
Q3. スタッフが回数券の提案に抵抗があるようです。どうすれば良いでしょうか?
スタッフが回数券の提案に自信を持てない、あるいは抵抗を感じる場合、それは「売り込み」というネガティブなイメージが先行しているのかもしれません。この課題を解決するには、徹底した「落とし込み」と「教育」が不可欠です。
- 理念と目的の共有: 回数券が単なる「割引チケット」ではなく、「患者様の健康寿命を延ばす」という院の理念を実現し、患者様の根本改善や健康維持をサポートするためのツールであることをスタッフ全員が深く理解するよう徹底しましょう。同時に、院の安定経営に繋がる重要な「ビジネスモデル」であることも伝えます。
- マニュアルとロールプレイングの徹底: 初診から回数券の提案、そして継続までの流れを詳細なマニュアルとして整備し、スタッフが自信を持って話せるようになるまでロールプレイングを繰り返しましょう。マニュアルは、スタッフが施術やコミュニケーションに集中できるだけでなく、教え漏れを防ぎ、院長の教育負担を減らすというメリットもあります。
- 「ケースストック」「準備」「振り返り」サイクル: 新規患者様への対応ごとに「ケースストック(症例分析)」「準備(シミュレーション)」「振り返り(反省と改善)」のサイクルを回すことで、スタッフは実践的な経験を積み、同じ失敗を繰り返さずに成長できます。特に「振り返り」では、自身の対応を言語化し、上長とのすり合わせで具体的な改善点を明確にすることが重要です。
- 動画を活用した教育: 治療コンセプトの説明や、回数券提案のシミュレーションなどを動画化し、いつでも見られる環境を整えることも効果的です。これにより、スタッフは自分のペースで学習でき、説明の質のばらつきも抑えられます。
- 承認と達成感: 回数券販売の目標達成を適切に評価し、個々の努力や成果を認め、賞賛することで、スタッフのモチベーションは大きく向上します。
Q4. 回数券の有効期限は設けるべきですか?設けるならどのくらいが適切ですか?
回数券に有効期限を設けることは、患者様の継続的な来院を促し、治療の中断を防ぐ上で非常に有効です。治療効果は継続的な来院によって得られることが多いため、期限を設定することで患者様のモチベーション維持にも繋がります。
適切な期間は、院の治療コンセプトや回数券の目的によって異なります。
- 集中治療期用(短期間):症状の早期改善を目指す回数券であれば、2〜3ヶ月など比較的短めの期間を設定し、集中的な来院を促します。例えば、〇回券で〇ヶ月以内という形です。
- メンテナンス・体質改善期用(長期間):治療効果の維持や根本的な体質改善を目指す回数券であれば、半年〜1年など長めの期間を設定し、定期的なメンテナンスを促します。
- 明確な説明:有効期限を設ける際は、購入時にその理由(治療効果の維持のためなど)を患者様に明確に伝え、納得してもらうことが大切です。
柔軟な対応として、やむを得ない事情(病気、転居など)がある場合は、個別に相談に応じる旨を伝えることで、患者様からの信頼を得ることにも繋がります。
Q5. 患者さんから回数券の返金を求められた場合、どう対応すべきですか?
患者様からの返金要求は、院の対応が問われる重要な場面です。まず基本として、**クレーム対応の原則である「誠意とスピード感のある対応」**を心がけましょう。
- 返金ポリシーの明確化: 回数券販売時に、返金に関する規定(有効期限内の未使用分のみ、手数料についてなど)を明確に説明し、書面で渡しておくことが重要です。これにより、患者様は安心して購入でき、トラブルを未然に防ぐことができます。
- 真摯な傾聴と共感: 返金要求があった場合は、まず患者様のお話を真摯に傾聴し、その背景にある不満や不安に共感する姿勢を見せましょう。患者様が不満を感じた具体的な原因を把握することが、解決への第一歩です。
- 原因の分析と改善: 返金に至った原因が、治療効果への不満、接客への不満、説明不足などであれば、それを真摯に受け止め、院全体の改善に活かしていくことが、今後の信頼構築に繋がります。
- 専門家への相談:返金に関する法的な側面や具体的な対応については、事前に弁護士などの専門家に相談し、適切なポリシーを策定しておくことをお勧めします。
返金は避けたい事態ですが、適切な対応は、患者様の不満を最小限に抑え、時には新たな信頼関係を築くきっかけにもなります。
Q6. 回数券導入後も患者さんとの関係性を維持・強化するための秘訣はありますか?
回数券を導入して終わり、ではありません。購入後も患者様との関係性を深め、長期的なファンになってもらうための継続的な取り組みが重要です。
- 患者教育の継続: 治療の必要性や健康維持の重要性について、来院ごとに患者様へ教育を続けることが大切です。例えば、インナーマッスルの重要性やセルフケアの方法などを動画で提供することも有効です。
- ニーズの変化への対応: 患者様の症状が改善するにつれて、求める価値は変化していきます。痛みの緩和だけでなく、再発予防、健康増進、さらには美容や運動など、患者様の「移ろう価値」を捉え続け、それに合わせた提案をしていくことが重要です。
- 定期的なコミュニケーション: ニュースレターの発行、誕生日のお祝いメッセージ、季節ごとの健康情報の発信など、定期的に患者様との接点を持つことで、来院頻度が下がっても関係性を維持できます。LINE公式アカウントを活用し、自動応答メッセージやリッチメッセージでスムーズな情報提供を行うのも良いでしょう。
- サービス品質の維持・向上: お出迎え・お見送り、丁寧な接客、技術の向上など、基本的なサービス品質を常に高く保つことが、患者様からの信頼とロイヤルティを高める基盤となります。
- 感動体験の提供: 患者様が「この院に来て良かった」と心から思えるような「感動的な体験」を提供し続けることが、紹介や口コミに繋がり、院の持続的な成長を支えます。
6️⃣回数券を成功させるポイントとは?考え方と実行のヒント
整骨院経営において、回数券は単なる割引チケットではありません。適切に活用することで、患者様の健康への貢献、院の安定経営、そしてスタッフの働きがい向上という、多岐にわたるメリットをもたらす強力なツールとなります。ここでは、回数券を成功させるための具体的な考え方と実行のヒントについて深く掘り下げていきましょう。
⭐回数券がもたらす多角的なメリット
回数券を導入する目的は、単に売上を増やすことにとどまりません。その裏には、患者様、スタッフ、そして院全体の持続的な成長に繋がる深い意味合いがあります。
- 継続率の向上: 回数券が「やめる判断ポイント」をなくす効果 患者様が治療を途中でやめてしまう要因の一つに、「次の来院をどうするか」という判断の連続があります。特に、症状が少し落ち着いてくると、「もう大丈夫かな」「今日は忙しいし、また今度でいいか」といった気持ちが芽生えやすくなります。ここで回数券が威力を発揮します。 回数券は、患者様が「通院を継続する」ことを事前に決断し、まとまった費用を支払うことで、来院ごとの「やめる判断ポイント」をなくす効果があります。例えば、サブスクリプション(月々払い)のような継続課金システムは、さらにその判断機会を減らし、通院を習慣化させるのに役立ちます。 患者様は「せっかく買ったのだから通い切ろう」という意識が働き、治療へのモチベーションを維持しやすくなります。その結果、計画通りの継続的な治療が可能となり、より高い治療効果へと繋がりやすくなるのです。 大切なのは、単に回数券を販売するだけでなく、患者様が「この回数券で得られる価値は、支払う価格よりも大きい」と感じ続けてもらうこと。患者様が感じる価値が価格を下回った時に、離反(来院中断)は起こりやすくなります。常に患者様が「通い続けたい」と思えるような、感動的で質の高い施術とサービスを提供し続けることが、回数券による継続率向上の土台となります。
- 安定した収入源の確保: 経営の予測可能性を高める 都度払いの場合、毎月の患者数や来院頻度によって売上が大きく変動しやすく、経営計画を立てにくいという課題があります。しかし、回数券を導入することで、まとまった売上を事前に確保できるため、院の収入が安定し、経営の予測可能性を飛躍的に高めることができます。 これにより、設備投資や人材採用、スタッフの教育など、将来に向けた経営戦略をより計画的に実行できるようになります。例えば、若松柔整株式会社の事例では、回数券と会員制の併用モデルを導入することで、予算未達時に回数券のキャンペーンを実施して売上を調整するなどの強みを持っています。 「三者の利益」(患者様・スタッフ・会社)という経営判断の指針において、院の利益を適切に確保することは、スタッフへの還元や福利厚生の改善、ひいては患者様へのより質の高いサービス提供に繋がる重要な要素です。回数券は、その安定的な利益確保に貢献するのです。
- 患者様の健康寿命への貢献: 継続的なケアによる根本改善と健康維持 多くの整骨院の治療コンセプトは「健康寿命を延ばす」ことにあるはずです。一回の施術で痛みが一時的に和らいでも、根本原因が改善されなければ再発のリスクは高まります。回数券は、患者様がその場の痛みを取るだけでなく、根本改善や健康維持のために継続的に通院することを促す最適な手段となります。 「痛み」にフォーカスするだけでなく、「再発しない身体づくり」や「やりたいことがもっとうまくできるようになる(健康増進)」といった、患者様の「理想の未来(ベネフィット)」に焦点を当てた治療理念を持つことが重要です。回数券は、この理想の未来を共に目指すための「通院計画」そのものなのです。 来院ごとに、患者様への「健康教育」を継続することも大切です。例えば、自宅でできるセルフストレッチの方法や、インナーマッスルの重要性などを動画で提供することで、患者様は自身の健康への意識を高め、より積極的に治療に臨むことができるでしょう。
- スタッフの負担軽減とモチベーション向上: 提案の「型」があることで心理的負担が減る 回数券の提案は、「売り込み」というイメージからスタッフにとって心理的な負担になりがちです。しかし、効果的な「提案の型」(マニュアルやスクリプト)を整備することで、この心理的負担を大きく軽減し、スタッフが自信を持って提案できるようになります。 マニュアルは、成果が出ているスタッフの「やり方」をそのまま言語化・体系化した「攻略本」のようなものです。これにより、スタッフ間の提案の質にばらつきがなくなり、誰でも一定以上の成約率を出すことが可能になります。 また、マニュアルやスクリプトは常に更新され、スタッフはそれを最大限活用することで成果を出しやすくなります。結果として、患者様からの「ありがとう」が増え、目標達成による達成感を得ることで、スタッフのモチベーション向上に繋がります。これは、単に「売り込み」ではなく、「患者様の健康に貢献している」という意識付けにもなります。院全体で、回数券の重要性を理解し、教育体制を充実させることが、スタッフの成長と定着に不可欠です。
- 生産性の向上: 非生産時間の削減と予約枠の最大化 回数券の導入は、院の「生産性」向上にも直結します。患者様が事前に支払い済みの回数券を持っていることで、受付での都度精算の手間が省け、会計業務の効率化が図れます。 さらに、患者様への説明(治療コンセプト、通院計画、自宅でのケアなど)を動画化し、来院時に視聴してもらうことで、施術者が同じ説明を何度も繰り返す必要がなくなります。これにより、施術者は「生産時間」(患者様への施術時間)を最大化でき、非生産時間(説明時間、事務作業、空き時間など)を削減することが可能になります。 削減された時間は、他の患者様への対応や電話対応、カルテ整理などに充てることができ、結果として少ないスタッフ数でより多くの患者様を対応できるようになり、院全体の予約枠の最大化と生産性の大幅な向上が期待できます。
- 卒業型コンセプトとの整合性: 継続型コンセプトへの転換の重要性 多くの整骨院は、患者様の症状が改善したら「卒業」という「卒業型コンセプト」を持っているかもしれません。しかし、回数券を成功させるためには、この考え方から**「継続型コンセプト」への転換**が非常に重要になります。 「痛み」がなくなったら終了、ではなく、「痛みが再発しない身体づくり」や「健康を維持・増進していく」という長期的な視点での価値提供へと治療コンセプトをアップデートしましょう。回数券は、その長期的な通院計画に沿った商品設計(例:集中治療期用、メンテナンス期用など)とすることで、患者様にとっての価値を最大限に高めることができます。 初診時の問診からクロージングまでの流れで、患者様の「顕在ニーズ」(痛み)だけでなく、その奥にある「潜在ニーズ」(痛みがなくなったら何をしたいか、どうなりたいか)を引き出し、それを治療のゴールとして共有することが重要です。そして、そのゴール達成のために「どれくらいの期間、どのような治療が必要か」を明確に提示し、回数券がその通院計画を円滑に進めるための「通いやすい選択肢」であることを伝えるのです。この「患者様主導型の患者指導」こそが、回数券成功の鍵となります。
⭐実行のヒント
回数券を成功させるためには、これらの考え方を日々の業務に落とし込むための具体的な行動が必要です。
- 治療コンセプトの再定義と共有: 院の「何屋」であるかを明確にし、全員が同じ「治療コンセプト」を言語レベルで共有する。痛みを取るだけでなく、その先の健康維持や健康増進までを見据えた継続的な価値提供を理念とする。
- 初診対応の徹底: 問診、検査、治療提案、治療、治療計画、クロージングの一連の流れをマニュアル化し、スタッフ全員が患者様のニーズを引き出し、治療の必要性と回数券のメリットを適切に伝えられるようにトレーニングを徹底する。特に、治療効果を視覚的、聴覚的、体感覚的に実感してもらう「プレ施術」や「ビフォーアフターの見せ方」は非常に有効です。
- スタッフ教育の継続: マニュアルやスクリプトを活用したロールプレイング、成功事例の共有、動画による学習など、スタッフが自信を持って回数券を提案できるような教育体制を構築・継続する。
- 価格設定と期間設定の最適化: 治療コンセプトに基づいて、ゴール達成に必要な回数と期間を考慮した回数券を設定し、お得感を明確に伝える。
- 患者様とのコミュニケーション強化: 回数券購入後も、患者様との関係性を維持・強化するための定期的な情報発信(ニュースレター、LINEなど)や、ニーズの変化に合わせた柔軟な提案を心がける。
回数券の成功は、単なる販売戦略ではなく、患者様への深い理解と、その健康に貢献したいという院全体の強い想い、そしてそれを支える仕組みとスタッフの力が融合して初めて実現するものです。ぜひ、これらのポイントを参考に、あなたの院の回数券を成功へと導いてください。
7️⃣まとめ&困ったときの相談先
🔑回数券は、単なる「割引」ではなく「未来への投資」
このコラムでは、整骨院経営における回数券の重要性と、その導入・運用を成功させるための具体的な方法を解説してきました。回数券は、単なる割引チケットではありません。それは、患者様が健康な未来を手に入れるための「通院計画」であり、院が安定した経営基盤を築くための「経営戦略」であり、スタッフがやりがいを持って働けるようになるための「教育ツール」でもあります。
売上が伸び悩む、患者様が定着しない、スタッフの教育に悩む…これらの課題は、回数券の戦略的な導入と運用によって大きく改善される可能性があります。
🔑今すぐできる、小さな一歩
いきなりすべてを完璧にしようとする必要はありません。まずは以下の「小さな一歩」から始めてみませんか?
- 院の「治療コンセプト」を改めて見つめ直し、言語化してみる。
- スタッフ全員で「なぜ回数券を導入するのか?」を話し合い、目的を共有する。
- 初診患者様への説明で「真のニーズ」を聞き出す質問を一つ増やしてみる。
最後に…
「回数券を導入したいけど、具体的にどう進めたら良いかわからない…」 「スタッフ教育のマニュアルをどう作ればいいのか悩んでいる…」 もし、このようなお悩みをお持ちであれば、ぜひ一度ご相談ください。
現在、整骨院の回数券導入と継続率アップに特化した「無料レポート」を配布しています。このレポートでは、このコラムではお伝えしきれなかった具体的な事例や、すぐに使えるトークスクリプトなどを掲載しています。
また、より個別の状況に合わせたアドバイスをご希望の方には、無料の個別相談も承っております。あなたの院の状況を丁寧にお伺いし、最適な回数券モデルの設計から、スタッフ教育、運用方法まで、具体的にご提案させていただきます。
あなたの院の持続的な成長を、心から応援しています。
まずは無料個別相談で整骨院経営のお悩みを解決!

弊社の整骨院・接骨院・整体院の経営専門のコンサルタントが、初回のみ無料で個別相談をご対応させて頂きます。
・売上を伸ばしたいが、何から始めればいいのかわからない
・患者様数を増やしたいが、何から始めればいいのかわからない
・採用をしたいが応募が全然こない
・事業拡大に伴い、育成環境や評価制度を整備したい
など、様々な経営のお悩みに対応しております。
是非、無料個別相談をご活用ください。
船井総研ならではの治療院経営の現場最新情報&ノウハウが満載の無料メールマガジン
自費治療で売上が月200万円以上UP!新規交通事故患者が毎月8名以上集まる!
その秘密を無料メルマガで大公開!!