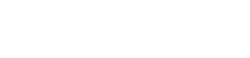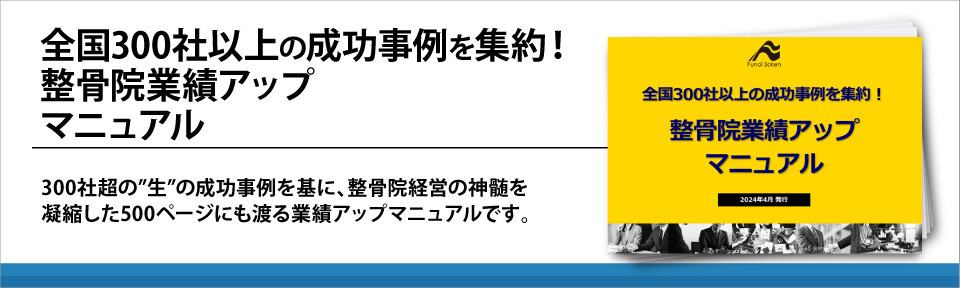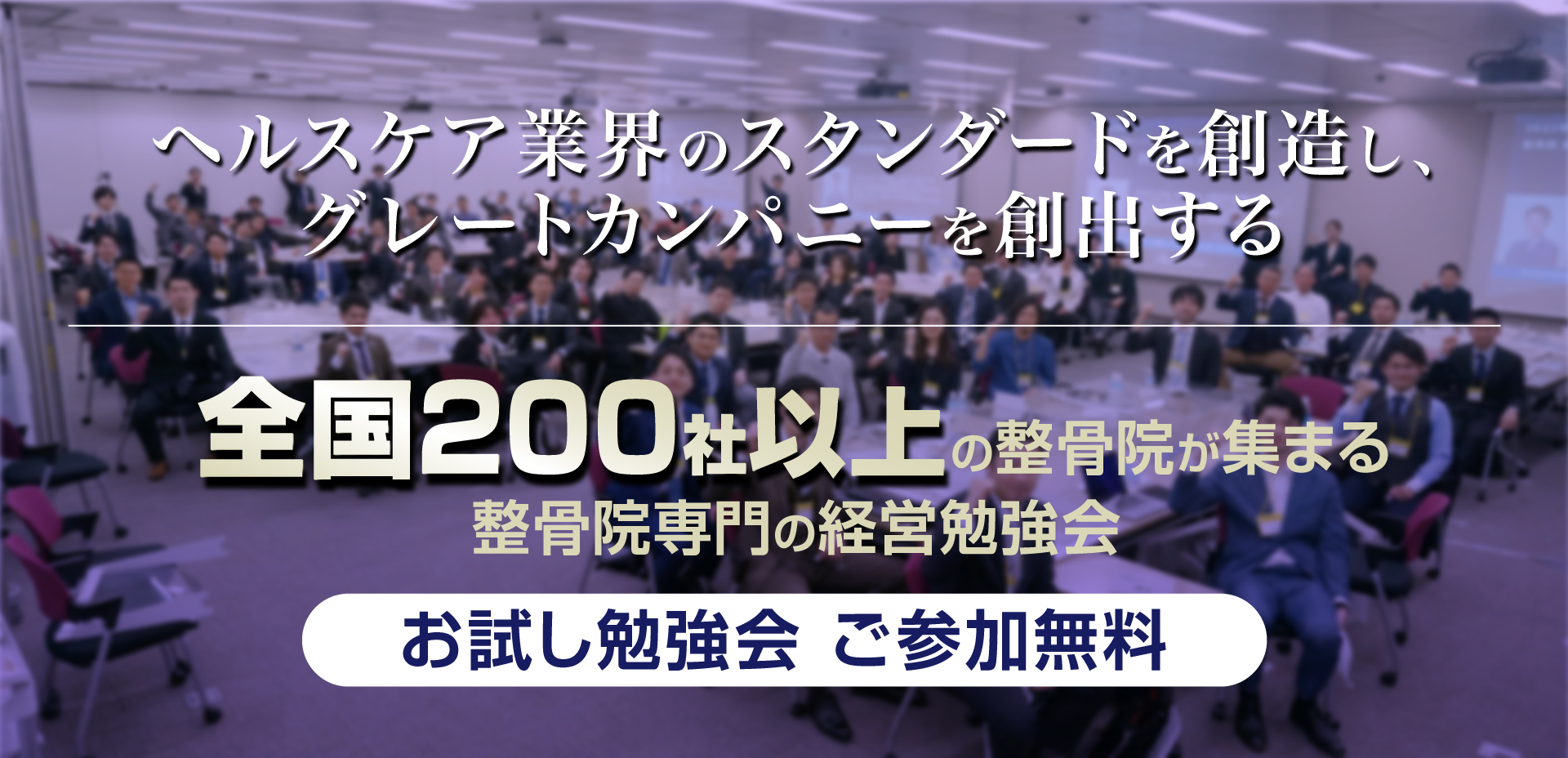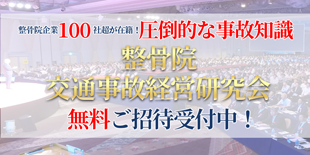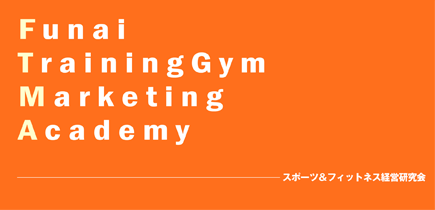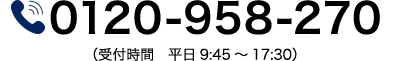Table of Contents
1. この記事はこんな方におすすめ
「患者さんの反応はいい。感謝の言葉ももらう。でも、紹介がほとんど出ない」
「紹介キャンペーンをやっても、思ったほど反応がない」
「広告費がかさむ一方で、紹介に頼れずジリジリしている」
こうした悩みを抱える整骨院経営者の方は、決して少なくありません。
ある院長先生は、こんなふうに話してくれました。
「患者さんに“よかったらご紹介くださいね”って伝えてるんですよ。でも実際には誰も紹介してくれない。こちらから何度もお願いするのも気まずくて…」
実はこれ、“紹介が生まれにくいパターン”の典型です。
📌 紹介が自然に出ている整骨院には、いくつかの共通点があります。
それは――
・声かけの“タイミング”
・紹介しやすい“伝え方の設計”
・スタッフも巻き込んだ“しくみ”
この3つが整っているかどうかで、紹介の出方は大きく変わります。
本記事では、
✔ なぜ紹介が起きないのか?
✔ 紹介が生まれる“ベストなタイミング”とは?
✔ 「紹介してください」とお願いせずに紹介が増える院の仕組み
といった視点で、現場ですぐに実践できるヒントをお伝えしていきます。
2. 整骨院・整体院が直面する“紹介が増えない”課題とは?
紹介は「患者さんが勝手にしてくれるもの」
そんなふうに思っていませんか?
実は、紹介が増えない整骨院にはいくつかの“構造的な理由”があります。
❶ タイミングが曖昧になっている
患者さんが誰かを紹介しようとするのは、**「あの人にも教えてあげたい」と思った“瞬間”**に限られます。
そのタイミングをうまくキャッチできるかどうかが、紹介の成否を左右します。
ところが多くの院では、「紹介してくださいね」と伝えるタイミングがバラバラ。
初診で早すぎたり、通い慣れてからは伝え忘れたり…。
その結果、患者さんは「誰かに紹介しようかな」と思うきっかけを逃してしまうのです。
紹介は“自然発生”ではなく、“設計されたタイミング”からしか生まれません。
❷ 紹介のハードルが高くなっている
患者さん自身が院のファンだったとしても、「人を紹介すること」は別問題です。
例えば――
・誰を紹介していいかわからない
・紹介した相手に気を遣わせないか心配
・「お金がかかる場所」を勧めることに抵抗がある
・なんとなく“営業っぽく”感じてしまう
このような心理的なブレーキが働き、「紹介してあげたい」気持ちがあっても行動に移せないのです。
さらに言えば、患者さん自身も「紹介のやり方がわからない」ということも。
LINEで送る?名前を伝える?付き添って来る?
ルールが曖昧だと、それだけで“めんどう”という印象になってしまいます。
❸ スタッフ側の“声かけストレス”
紹介を促す声かけをする側――つまりスタッフや先生自身が「気まずさ」や「負い目」を感じている場合もあります。
-
「紹介してください」と言って反応が薄いと気まずい
-
“押し売り”と思われたくなくて、自信を持って言えない
-
忙しいと、つい声かけを忘れてしまう
このように、紹介の声かけが“義務感”や“営業っぽさ”になってしまうと、スタッフ自身の心理的負担が大きくなります。
結果的に、紹介を促すシーンが減り、「一応伝えましたけど…」という形だけのアプローチになってしまいがちです。
紹介が生まれない理由は、施術の質ではなく、“しくみと心理設計の不足”にあります。
次のパートでは、こうした課題を超えるカギとなる、
📌「紹介が自然に生まれる“タイミング”の設計」について、現場で使える実例とともに解説していきます。
3. 対策を取らないとどうなる?放置リスクと現実的な課題
「紹介がないなら広告を回せばいい」
「今は目の前の患者さんに集中しよう」
そう考えて“紹介の仕組み”を後回しにしてしまうと、実はじわじわと院の土台が弱っていきます。
ここでは、紹介が生まれない状態を放置したときに起こる、4つの現実的なリスクをご紹介します。
📉① 広告費の依存体質にハマる
紹介が出ない状態では、どうしても集客を広告に頼るしかなくなります。
広告は“費用をかけ続けなければ止まる”性質のもの。長期的に見れば、安定した経営とは真逆の状態です。
しかも今は、PPC広告もSNS広告も費用対効果が悪化しやすく、競合院との“消耗戦”になりやすい状況。
紹介がない=未来の利益率が下がる構造に直結してしまうのです。
💭② スタッフが「がんばっても報われない」と感じる
紹介がまったく出ない状態が続くと、現場のスタッフが「空回り感」を覚えはじめます。
-
一生懸命に接客・施術しても、“誰かに伝わっていく”実感がない
-
自分の頑張りが“院の成長”に結びついていないように感じる
-
声かけをしても反応がなく、だんだん言いづらくなる
こうした状態では、スタッフのモチベーションや定着にも悪影響が出てしまいます。
⏳③ 紹介の“チャンス”を逃し続けてしまう
紹介は、患者さんの“感動”や“共感”の中にある一瞬のきっかけから生まれます。
でも、そのタイミングを逃し続けてしまうと、本来あったはずの紹介が“無かったこと”になってしまうのです。
例えば、「あの人に紹介したいかも」と思っていたのに、何も仕掛けがなかったために忘れられてしまう。
こうした“機会損失”が年間で積み重なれば、30件、50件という差になっていきます。
🚫④ 紹介疲れ・逆効果を引き起こすリスク
そしてもう一つ怖いのが、“紹介ばかりお願いされている”と感じた患者さんの心理反発です。
最初は気持ちよく通ってくれていた患者さんでも、
「また紹介の話か…」「毎回何か頼まれている気がする」と感じさせてしまうと、
紹介どころか離脱のきっかけにもなりかねません。
紹介は“感謝される行為”であるべきなのに、
やり方を間違えると“負担になる行為”に変わってしまうのです。
紹介が出ない状態を放置すると、
“出せるはずだった紹介”を失うだけでなく、
“患者さんの信頼やスタッフの熱意”まで消耗させてしまうリスクがあります。
次のパートでは、こうした負の連鎖を断ち切る「紹介が自然に生まれる仕組み」について、タイミングと設計の具体例を交えて解説していきます。
4. まず取り組みたい基本的な“紹介が生まれる設計”
紹介を増やすために、まずやるべきこと。
それは、「紹介してください」とお願いすることではありません。
紹介とは、**“設計された流れの中で、患者さんが自然としたくなる”**からこそ、持続的に増えていくのです。
ここでは、紹介が自然に生まれている整骨院が実践している「3つの基本設計」について、詳しく解説します。
✅① タイミング設計:「今その話?」にならない自然な流れをつくる
多くの整骨院でありがちなのが、紹介の声かけを“初回”でしてしまうこと。
たしかに初診時の感動は大きく、「いい先生に出会えた」と思ってもらいやすいタイミングではあります。
しかし実際には、初回は“患者さん自身の不安や痛み”が最も大きい時期。紹介どころではありません。
紹介が生まれやすいのは、
📌 信頼が芽生え、効果も実感し始める2〜4回目の来院時。
この時期は、患者さんの気持ちがこう変化していきます。
-
「この先生、信頼できるかも」
-
「ここに来て正解だったな」
-
「これなら誰かに教えてもいいかもしれない」
この“ポジティブな実感”が生まれるタイミングこそが、紹介のベストチャンス。
症状が少し楽になった、仕事や家事がやりやすくなった…そんな変化を感じた瞬間を逃さずに声をかけることが大切です。
▶ 例:タイミング設計の流れ(理想パターン)
-
初回:問診・検査・施術に集中(紹介の話はしない)
-
2回目:変化を確認 → 信頼のタネを育てる
-
3回目:改善実感を聞き取り → さりげなく紹介につなげる
→「○○さんのように困ってる方、周りにいませんか?」 -
4回目:紹介カードやLINEメニューで具体的な行動につなげる
✅② 伝え方設計:「頼まれた感」ではなく「共感したくなる流れ」をつくる
「紹介してください」――この言葉は、場合によってはプレッシャーにもなります。
特に日本人は、「誰かに勧める=責任が伴う」と無意識に感じてしまう傾向があります。
だからこそ、紹介を促す際は“お願い”ではなく、“共感と感謝”をベースにした伝え方が重要です。
▶ 患者心理を動かす伝え方の工夫:
-
「同じように悩んでる方がいれば、ぜひ力になりたいと思ってます」
-
「○○さんと同じような状態の方、結構多いんですよね…」
-
「これからは“症状が出る前”にケアする時代ですし、予防のきっかけになれば嬉しいです」
これらはすべて、紹介=患者さん自身が“誰かの役に立てる”行為に感じられるようにするトークです。
また、紹介した患者さんには「先生、○○さん連れてきました!」という達成感も生まれます。
そのときに感謝の気持ちを伝え、紹介された方にも丁寧に対応すれば、紹介の連鎖が生まれていきます。
▶「伝え方」失敗例あるある:
-
「紹介カードあるので、よかったら配ってください」→ 誰に? いつ? どうやって?がわからず終わる
-
「今キャンペーンやってます」→ お得感だけが強く、“誰のためか”が伝わらない
-
「たくさん紹介お願いします」→ 数のプレッシャーで重くなる
伝え方ひとつで、紹介は“行動”にも“遠慮”にもなります。
✅③ スタッフ導線設計:誰が・いつ・どう伝えるかまで決めておく
最後のポイントは、“院全体で紹介が生まれる体制を整えておくこと”です。
いくら先生が素晴らしい声かけをしても、受付で流れが切れたり、全員が紹介の重要性を理解していなかったりすると、取りこぼしが出てしまいます。
▶ 導線設計で決めておくべきこと:
-
どの来院ステージで声かけするか(2回目/3回目など)
-
施術スタッフ or 受付、どちらが主担当か(ダブルで伝えるのも◎)
-
紹介のきっかけツールを何にするか(紙のカード、LINEテンプレ、クチコミ依頼QRなど)
-
スタッフ全員が“紹介に対する価値観”を共有しているか(マニュアル化/ロープレなど)
▶ 実際の現場イメージ:
-
【施術後】「今、かなり動きが良くなってきましたね」
-
【反応が良い場合】「ご家族や職場の方で、同じような症状の方いませんか?」
-
【会計時】受付スタッフから「ご紹介いただいた方にも、特別な初回特典をご案内しています」
-
【フォロー】後日LINEで「○○さんがご紹介くださった方、無事来院されました。ありがとうございました!」
このように、院全体で“紹介の空気感”がつくれているかどうかが、安定した紹介数につながります。
紹介は「努力で増やすもの」ではなく、「仕組みで自然に増えるもの」。
次のパートでは、紹介に関して困ったときの相談先や、導線を可視化するチェックリストについてご紹介します。
5. “紹介が起きない…”で困ったときの相談先
「紹介は増やしたいけど、どこから改善すればいいか分からない」
「自分たちなりにやってるつもりなのに、結果が出ない…」
そんな声を、私たちはこれまで数多く聞いてきました。
実は“紹介が増えない院”には、共通するボトルネックがあります。
逆に言えば、成功している整骨院には、紹介が生まれる“型”があるということです。
📘 解決のヒント①:『整骨院業績アップマニュアル』
現在ご希望の方には、
📕 全国300院超の成功パターンを集約した《整骨院業績アップマニュアル》(最新版)を無料でご案内しています。
この中には、
-
紹介がゼロだった院が「毎月20件超」を安定化させた導線の作り方
-
スタッフが“楽しみながら”紹介トークを取り入れられる仕組み
-
LINEと紙を組み合わせた「2ステップ紹介」成功事例
など、現場で「実際に成果が出た具体策」が詰まっています。
「とりあえず試してみる」ではなく、“うまくいった事例”から逆算して自院に応用したい方にぴったりの内容です。
🤝 解決のヒント②:整骨院専門コンサルタントによる無料経営相談
もし、
-
自院に合う導線設計が分からない
-
スタッフの巻き込み方に不安がある
-
そもそも紹介以前に患者さんが定着しにくい
といったお悩みがある場合は、
📞 「整骨院特化の専門コンサルタント」による無料相談もご活用ください。
実際の院の課題をヒアリングした上で、
「●回目でこう声をかけると紹介につながりやすい」
「LINEでの声かけテンプレをこう設計しましょう」など、その場で改善策をご提案します。
現場経験のある担当者が対応しますので、ちょっとしたご相談からでも大歓迎です。
「紹介が出るかどうか」は、運やセンスではなく、設計と導線の差。
まずは自院にあった一歩を踏み出してみてください。
6. 紹介を生み出すポイントとは?考え方と実行のヒント
「紹介してください」
この一言だけで、自然に紹介が生まれる時代はもう終わっています。
現代の患者さんは、ネットで情報を調べ、比較検討をした上で来院しています。
そんな中で紹介を生み出すには、“心が動いた瞬間”に寄り添い、「紹介したくなる院」になる必要があります。
紹介を生み出す整骨院が実践している“考え方と仕掛け”。
ここでは、その本質を深掘りしていきます。
✅① 紹介は「満足」ではなく「感情」が動いたときに起きる
まず知っておきたいのは、紹介は論理ではなく感情の行動だということ。
たとえば、患者さんがこんなふうに感じたとき――
-
「ここに通い始めて、気持ちも軽くなった気がする」
-
「あの先生、私の話を本当に聞いてくれるんだよね」
-
「こんなに丁寧に説明されたの、初めてだったな」
こういった“ちょっとした感動”や“共感体験”こそが、紹介を後押しする引き金になります。
決して「施術効果が100点満点だから」ではなく、
**“その人にとって特別だったかどうか”**が、紹介の源泉です。
▶️ 現場でよくあるNGパターン:
-
「紹介は、施術で結果出せば自然と出るもの」
-
「技術が高ければ、患者さんは勝手に連れてくる」
この考えでは紹介は出にくいです。なぜなら、技術が良くても感情が動かないと人は行動しないから。
紹介は「伝えたくなる感情」が揺さぶられたときにしか生まれません。
✅② 「お願い」ではなく「共感と共有」で伝える
紹介が出ない院の多くは、「紹介してください」という表現だけに頼っています。
この言葉が悪いわけではありませんが、それだけだと“患者さん任せ”になってしまうのです。
紹介を生み出す整骨院では、声かけのベースが違います。
▶️ 良い声かけの例:
-
「最近、○○さんのように肩の痛みで悩んでる方がすごく増えてて…ご家族や職場の方にもいらっしゃいませんか?」
-
「○○さんの変化、僕たちもうれしいです。似たような症状の方がいたら、力になれると思うので、ぜひ教えてください」
-
「“ちゃんと話を聞いてくれる院”って、意外と少ないってよく言われるんですよ。もし周りで困ってる方がいたら、気軽にご紹介ください」
これらは、“患者さんの体験”をもとにした共有型トークです。
押しつけにならず、「誰かの役に立てるかも」と思ってもらえる導線になっています。
▶️ ポイントは、「紹介=善意の共有体験」として捉えてもらうこと。
紹介することで、相手にも、自分にも“いい影響がある”と思えた瞬間に、行動は生まれます。
✅③ 紹介は「文化」になって初めて持続する
紹介を“単発の施策”として終わらせないためには、
紹介を“院の文化”として根付かせることが欠かせません。
▶️ 院内文化として浸透させるための工夫:
-
紹介が出たら全員でシェアする → 受付・施術スタッフ関係なく「○○さんの紹介で新しい患者さんが来てくれました」と共有。
→ スタッフのやる気が上がり、「紹介って嬉しいことだよね」という共通認識が育ちます。 -
「紹介カード」や「LINE紹介ボタン」を目に触れる位置に置く → 毎回しっかり伝えなくても、“目に入るだけ”で紹介への心理的ハードルは下がる。
-
紹介があった人には、必ず“感謝”を返す → 直接のお礼や、LINEでのひとことでもOK。「紹介=評価されてる感覚」がモチベーションにつながる。
-
月に1回は“紹介のトーク事例”をスタッフで共有 → どんなトークが反応よかったか、言いやすかったかを話し合うだけで、全体のスキルが底上げされていきます。
紹介は“マーケティングの手法”というより、
院の空気感そのものが生み出す結果です。
紹介が起きている院は、「紹介してください」と無理に言わずとも、患者さんから「紹介してもいいですか?」という声が上がってきます。
✅④ スタッフにも“紹介に対する抵抗感”をなくす
もうひとつ重要なのが、スタッフの意識。
現場ではこんな声をよく聞きます:
-
「紹介って、営業っぽくて言いづらい…」
-
「失礼にならないかなと思って遠慮してしまう」
-
「忙しくてつい言い忘れてしまう」
このような“心のブレーキ”を外すには、紹介の捉え方を変えていく必要があります。
▶️ スタッフ教育で意識したいこと:
-
「紹介は、良いことを広げる行為」だと伝える
-
「患者さんに喜ばれている経験」を思い出してもらう
-
「誰かの役に立てるって嬉しいよね」というマインドを共有する
紹介は、患者さんと“信頼関係があるからこそ生まれる”ものであり、
**声かけはその信頼を「次につなげる行為」**です。
この価値観がチームに浸透すると、紹介の声かけが自然になり、誰も無理を感じず行動できるようになります。
🎯まとめ:紹介は技術ではなく「設計された空気感」
紹介を増やすには――
-
感情が動く瞬間を拾う
-
押しつけではなく共感でつなぐ
-
スタッフ全員が「紹介=良いこと」と思える文化を育てる
この3つが揃ったとき、紹介は**「狙って生み出せる現象」**になります。
そしてそれは、リピート率や口コミ、LTV(生涯顧客価値)にも直結していく、まさに“院の未来をつくる仕組み”になるのです。
7. よくある質問(Q&A)
ここでは、実際に整骨院経営者からよくいただく“紹介に関する質問”とその解説をまとめました。
現場でよくある迷いや誤解も多く含まれているので、ぜひチェックしてみてください。
❓Q1. 紹介キャンペーンって効果あるんですか?
✅ A. 一時的なきっかけにはなりますが、“仕組み”がなければ続きません。
紹介キャンペーンは、あくまで「紹介のきっかけ」をつくるための“導線のひとつ”です。
確かに「紹介で初回無料」や「紹介者に特典」などは興味を引きますが、その場かぎりの“プレゼント目当て紹介”で終わる可能性も高いです。
むしろ、紹介が自然に起きる院は「キャンペーンがなくても紹介が出る仕組み」を先に整えています。
キャンペーンを打つなら、その前に“紹介の動線・タイミング・伝え方”をしっかり設計することが重要です。
❓Q2. 紹介をお願いしても断られることがあって…どう対処すれば?
✅ A. 「断られた=嫌われた」ではありません。心理的ハードルを一緒に下げましょう。
紹介を断られることは、決して“人間関係の否定”ではありません。
-
紹介の方法が分からない
-
誰を紹介したらいいか思いつかない
-
相手に気を遣わせたくない
こうした“相手の事情”が背景にあるケースがほとんどです。
ですので、断られても気まずくならずに、
「また気になる方がいたら教えてくださいね」
「タイミング合えば、いつでもお声がけください」
と、やんわりした声かけをしておくことで、数ヶ月後にふと思い出してもらえることも多いです。
紹介は“今すぐ起きるもの”ではなく、“じわじわ育つ関係性”と考えましょう。
❓Q3. Google口コミやSNS投稿はどう頼めばいいですか?
✅ A. 「お願いベース」より「共感・感謝ベース」の伝え方が効果的です。
よくある声かけがこちら:
「よかったら口コミ書いてくださいね!」
もちろん間違いではありませんが、少し“こちらの都合”が見えてしまう表現でもあります。
代わりに、こんなふうに伝えると反応が変わります。
「○○さんみたいに悩んでる方にとって、口コミってすごく参考になるんですよ」
「もし○○さんのお言葉で気持ちが軽くなる方がいたら、すごくありがたいです」
“人のために役立てる”という視点を入れるだけで、患者さんの行動意欲が大きく変わります。
また、「●●のURLをLINEでお送りしますね」と、投稿までのハードルを下げておくと、より実行率が高まります。
このように、“紹介”や“口コミ”に関する悩みには、
ちょっとした設計の見直しで解決できることがたくさんあります。
8. まとめ:紹介が自然に生まれる整骨院の共通点とは?
紹介を「運任せ」にしている整骨院と、
紹介が「安定的に出ている」整骨院の違いは何でしょうか?
それは――
✅ タイミングを理解し、
✅ 伝え方を設計し、
✅ スタッフ全員で仕組み化しているかどうかです。
紹介が自然に生まれる院には、共通する“空気感”があります。
-
初診〜数回目のうちに「感情が動く体験」が設計されている
-
スタッフ全員が「紹介=患者さんのためになる」と確信している
-
声かけにブレがなく、患者さんにとって“言いやすく、行動しやすい”
紹介は、ちょっとしたコミュニケーションの積み重ねと、
“誰かのために伝えたくなる”と思ってもらえる体験によって生まれます。
一方で、やり方を間違えれば――
-
「また紹介か…」と患者さんに引かれてしまう
-
スタッフが言いづらくなり、誰も声をかけなくなる
-
結局、広告だけに頼る“苦しい集客サイクル”から抜け出せない
という負のループにもなりかねません。
だからこそ、紹介対策は「設計」であり「戦略」です。
それは、決して難しいものではなく、“成功パターンを知り、自院に合う形で実践していく”ことがポイントです。
📘 まずは一歩踏み出したい方へ
-
成功している整骨院が、どんな流れで紹介を生み出しているのか?
-
スタッフを巻き込むには、どんなマインドセットと仕組みが必要なのか?
その答えをまとめたのが、
👉 **《整骨院業績アップマニュアル》**です。
全国300院超の成功事例と再現可能な導線を集約しています。
📞 さらに、自院の課題に応じて方向性を相談したい方は、
👉 整骨院専門のコンサルタントによる無料相談をご利用ください。
現場経験に基づいた具体的なアドバイスが、きっと新しいヒントになるはずです。
紹介は、未来の整骨院経営を左右する“静かな差”です。
いま紹介が出ていないからこそ、
このタイミングで「紹介が起きる設計」を整えていきましょう。
まずは無料個別相談で整骨院経営のお悩みを解決!

弊社の整骨院・接骨院・整体院の経営専門のコンサルタントが、初回のみ無料で個別相談をご対応させて頂きます。
・売上を伸ばしたいが、何から始めればいいのかわからない
・患者様数を増やしたいが、何から始めればいいのかわからない
・採用をしたいが応募が全然こない
・事業拡大に伴い、育成環境や評価制度を整備したい
など、様々な経営のお悩みに対応しております。
是非、無料個別相談をご活用ください。
船井総研ならではの治療院経営の現場最新情報&ノウハウが満載の無料メールマガジン
自費治療で売上が月200万円以上UP!新規交通事故患者が毎月8名以上集まる!
その秘密を無料メルマガで大公開!!