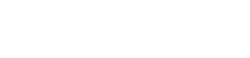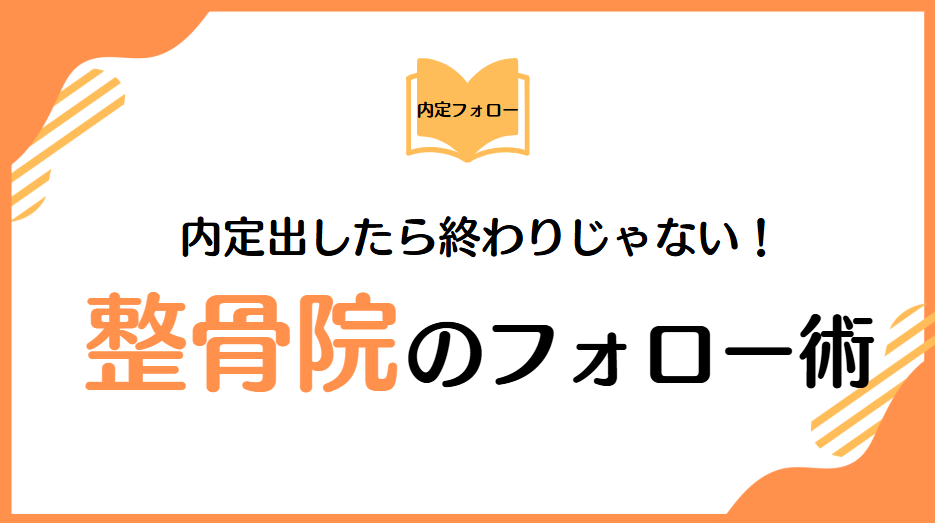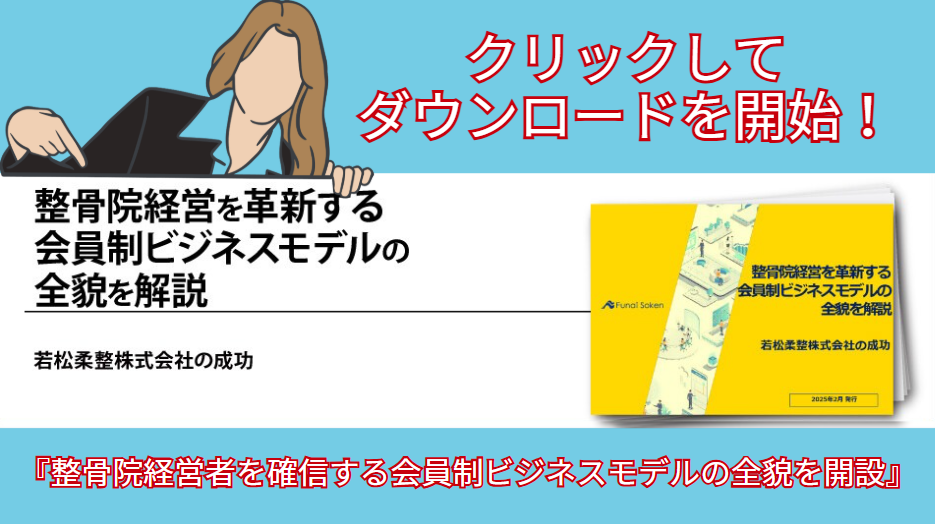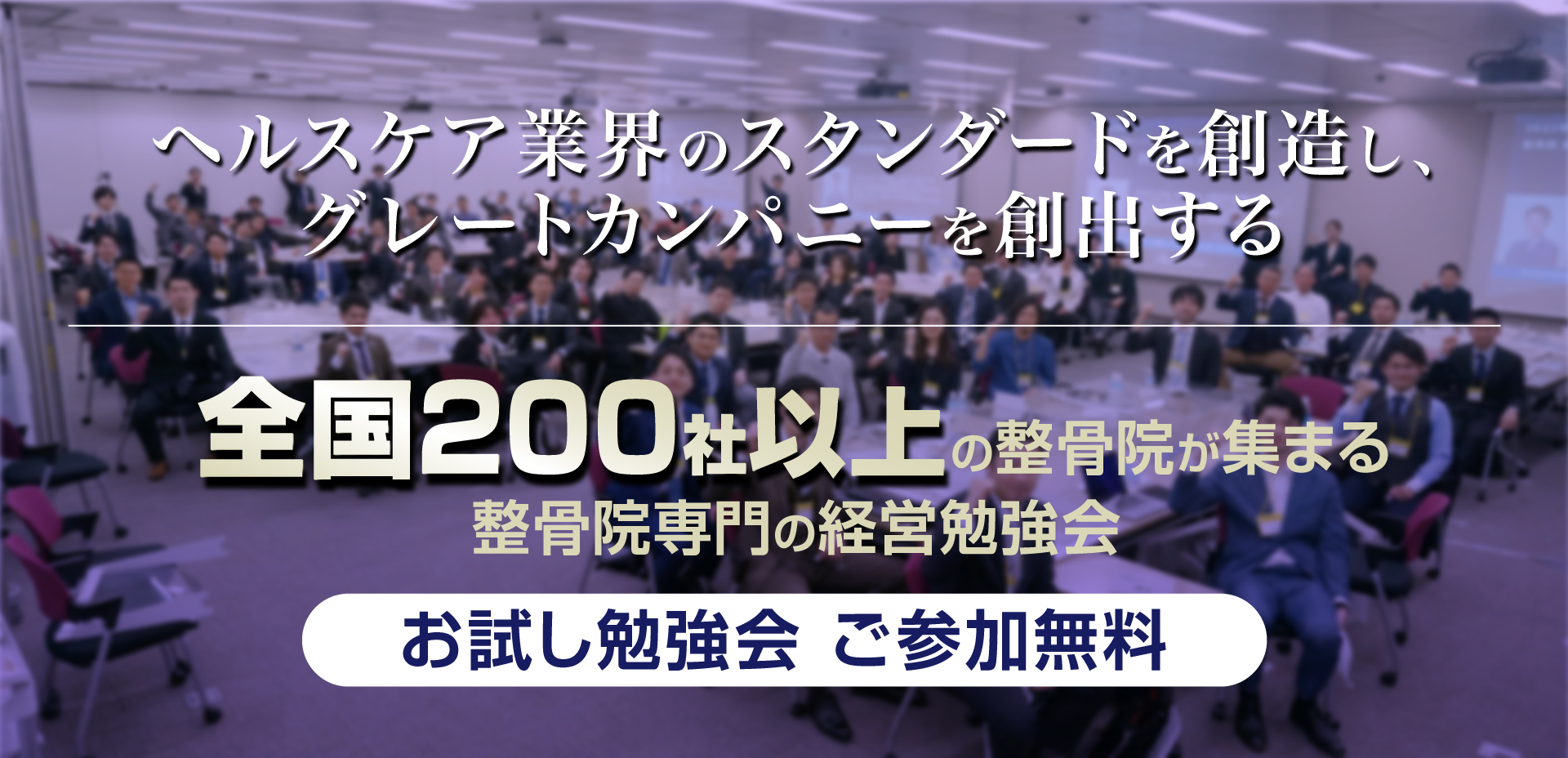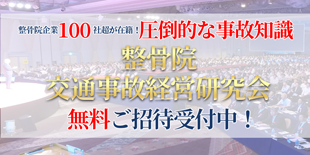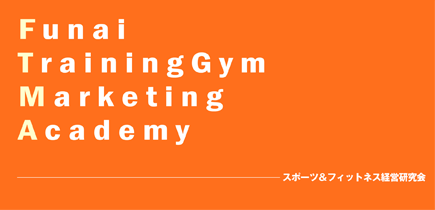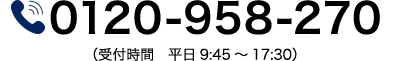Table of Contents
内定出したら終わりじゃない!辞退されない整骨院のフォロー術
1. この記事はこんな方におすすめ
整骨院経営者の皆様、こんにちは!
新しい仲間を迎えることは、院の活気を高め、未来を切り拓く大切な一歩ですよね。特に、新卒採用は、長期的な視点で組織を強化していく上で欠かせない投資と言えるでしょう。しかし、時間も労力もかけて「この人だ!」と決めた内定者が、残念ながら辞退してしまう…そんな経験はありませんか?
このコラムは、まさにそんなお悩みを抱える皆様のために書かれました。具体的には、以下のような方々にとって、きっとお役立ていただける内容となっています。
✓新卒採用に力を入れているが、内定辞退に悩んでいる整骨院経営者の方
✓内定者との関係構築やモチベーション維持に不安を感じている方
✓せっかく採用した新卒が早期離職してしまうことに悩んでいる方
✓採用活動の費用対効果を最大化し、安定した組織基盤を築きたいと考えている方
新卒採用は、ただ頭数を揃えるだけでなく、理念を共有し、共に成長できる仲間を迎え入れる「理念共感型採用」が重要です。採用の失敗は教育では取り戻せない、とも言われます。このコラムを通じて、皆様の採用活動が成功し、院の発展に繋がることを願っています。
2. 新卒採用における内定辞退とは?
新卒採用において、内定を出すということは、貴院の未来を託す大切な人材を見つけ出した、喜ばしい瞬間であるはずです。しかし、実は内定を出しただけでは、採用活動は完了したとは言えません。むしろ、ここからが「真の採用活動」の始まりなのです。
✅内定辞退が単なる手続きの終了ではないことの再認識
多くの経営者様は、内定を出した時点で一安心されるかもしれません。しかし、内定者が入社を辞退するということは、単なる採用プロセスの途中でストップする、という事務的な問題に留まりません。これは、貴院がこれまで投じてきた採用コスト(時間、労力、費用)が水泡に帰すだけでなく、未来の組織を担うはずだった貴重な人材を失うことを意味します。
整骨院業界では、柔道整復師の養成校が増えた結果、資格者が急増し「供給過多」が懸念される時代がありました。しかし現在は、資格者の採用が難しくなっており、リクルートを制する企業が勝つと言われるほど、人材確保が競争優位性において重要なポイントとなっています。だからこそ、一人ひとりの採用の重みを再認識する必要があります。
✅採用活動における「LTV(Life Time Value)」の視点の重要性
患者様に対して「LTV(顧客生涯価値)」という言葉を用いるように、採用においても、このLTVの視点が非常に重要です。つまり、採用した人材が、入社後にどれだけの期間、どれだけの価値を組織にもたらしてくれるか、という長期的な視点を持つことです。内定辞退は、この「従業員LTV」がゼロになることを意味します。
せっかく見込みの高い人材を見つけたのに、入社前に「辞退」されてしまうことは、まさに大きな損失です。貴院の理念に共感し、長く活躍してくれる人材を確保するためには、内定を出してから入社までの期間をいかに有意義に過ごし、内定者のエンゲージメントを高めるかがカギとなります。
✅人材不足の時代において「採用の失敗は教育で取り返せない」という考え方
これは、どんなに優れた教育プログラムを用意しても、そもそも貴院の理念や文化に合わない人材を採用してしまえば、高いモチベーションを維持し、長く活躍してもらうことは難しい、という意味です。単なる「即戦力」を求める採用だけでは、組織の純度が低下し、早期離職につながるリスクがあるのです。
だからこそ、採用の初期段階から「理念共感型採用」を徹底し、貴院のビジョンや価値観に深く共感し、共に成長できる「仲間」を集めることが重要になります。個人のビジョンと会社のビジョンが重なる「共感領域」を創出することで、「自分の為の努力が会社の為にもなり、会社の為の努力が自分の為にもなる」という好循環が生まれ、貢献実感が高まり、結果としてモチベーションの維持と定着に繋がります。
内定辞退を防ぐことは、単なる採用活動の効率化に留まらず、貴院の組織の「純度」を高め、長期的な成長を実現するための、極めて重要な経営課題なのです。
3. 対策を取らないとどうなる?内定辞退の放置リスクと現実的な課題
「内定を出したから、あとは入社を待つだけ」—もしそのように考えていらっしゃるなら、それは大きな落とし穴かもしれません。内定辞退は、単なる一人の採用失敗に留まらず、貴院の経営に多大な影響を及ぼす可能性があります。具体的なリスクと課題を深掘りしていきましょう。
✅1. 採用コストの増大と再採用の手間、計画の遅延
新卒採用には、多大なコストがかかっています。求人媒体への掲載費用はもちろん、採用活動に関わるスタッフの人件費、説明会や面接に費やす時間、採用ツールの作成費用など、目に見えないコストも膨大です。採用担当者の仕事は、母集団(学生接触数)の最大化とイベント誘導の最大化であり、そのために年間計画に基づいたイベント企画、準備、ツール作成、求人媒体への登録・最適化など多岐にわたる業務が発生します。また、採用活動管理シートで母集団形成から内定、内定承諾までの各フェーズの移行率やKPIを数値管理することも重要です。
せっかくこれらの投資をして内定を出しても、辞退されてしまえば、それまでのコストが無駄になり、再びゼロから採用活動を始めなければなりません。これは、採用計画の遅延を招き、人手不足が解消されないだけでなく、再度の採用活動にさらに費用と労力がかかるという悪循環に陥ります。売上管理と同様に、採用活動においても数値管理は必須です。
✅2. 組織運営への悪影響と、早期離職によるチームの純度低下リスク
内定辞退や、それに続く早期離職は、組織全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼします。まず、人員計画が狂うことで、既存スタッフへの業務負担が増加し、モチベーションの低下や疲弊に繋がりかねません。さらに、新しい人材が定着しない状況が続くと、組織の「純度」が低下するリスクがあります。
「採用の失敗は教育では取り返せない」という言葉があるように、理念や文化に合わない人材を採用してしまうと、いくら教育しても定着せず、組織全体のベクトルがずれてしまう可能性があります。
また、新卒が早期に離職してしまうと、既存スタッフは「また新人を教育するのか」という負担を感じ、教育者不足に陥ることもあります。社長が現場に出る時間を減らし、教育資料を作成し始めるなどの取り組みも必要になります。これは、チームワークの乱れや生産性の低下に直結し、結果として患者様へのサービス品質にも影響が出かねません。
経営者は、従業員にとって「社会人の親」のような存在であり、社員に学べる環境を内部でも外部でも提供するべきという考え方もあります。もし社員が会社から期待されていないと感じたり、愛されていないと感じたりすれば、モチベーションは低下してしまいます。
✅3. 求職者ニーズの変化に対応できないことの弊害
現代の求職者、特に新卒世代は、給与や待遇だけでなく、「柔軟な働き方へのニーズ」(拘束時間や休日、リモートワーク、フレックスタイム制の選択制など)、「研修制度の充実」、「明確なキャリアパス」などを重視しています。もし貴院が、こうした時代の変化に対応した採用活動や内定者フォローを行わなければ、いくら内定を出しても、より魅力的な条件を提示する他社に流れてしまうのは当然の流れと言えるでしょう。
給与訴求や完全週休2日制といった働き方だけを強調しすぎると、一時的に採用はうまくいっても、入社後に期待とのギャップが生じ、早期離職につながる傾向があることも指摘されています。長期的なキャリア形成支援を通じてエンゲージメントを高めることが重要です。
内定辞退は、単に「ご縁がなかった」で済ませられる問題ではありません。それは、貴院の採用戦略、組織体制、そして未来の成長への投資に直結する重要な課題なのです。
4. まず取り組みたい基本的な内定辞退防止対策
内定辞退を防ぐためには、内定を出した後のフォローだけでなく、採用活動の初期段階から入社に至るまでのプロセス全体を見直し、基本的な対策を徹底することが不可欠です。ここでは、特に重要となる4つのポイントをお伝えします。
✅1. 「理念共感型採用」の徹底と、面接時のお互いの見極め
採用活動において最も重要なのは、単に「頭数」を揃えることではなく、貴院の理念やビジョンに深く共感し、共に成長していける「仲間」を見つけることです。これを「理念共感型採用」と呼びます。即戦力だけを求める「即戦力採用」は、組織の純度を低下させ、結果的に中途採用者の退職や早期離職につながるリスクがあることが指摘されています。
面接は、会社側が一方的に評価する場ではありません。求職者と貴院が「お互いに合うかどうか」を見極める大切な機会です。この際、貴院の仕事観や求める働き方について、正直に、そしてはっきりと伝えることが重要です。例えば、「時間とお金の交換という働き方を望むのであれば、うちよりも楽なところはいっぱいあるから、絶対にそっちに行った方がいいよ」と明確に伝える企業もあります。
このように、貴院のビジョン、大切にしている価値観、そして具体的な働き方をcandidに伝えることで、求職者自身のビジョンと会社のビジョンが重なる「共感領域」を大きくすることができます。この共感領域が大きいほど、「自分のための努力が会社のためにもなり、会社のための努力が自分のためにもなる」という貢献実感が高まり、モチベーションの維持や定着に繋がるのです。また、候補者の企業の理念や価値観への共感、組織風土への適応力、一緒に働くメンバーとの協調性といった「カルチャーフィット」を見極めることも、非常に重要な要素となります。
✅2. 採用活動における数値管理の重要性とその具体例
売上や経営状況を数値で管理するように、採用活動もまた数値で管理することが成功への鍵です。「採用活動管理シート」や「母集団管理シート」を活用し、以下のKPI(重要業績評価指標)を明確にして追跡しましょう。
- 目標採用人数
- 母集団形成数(学生接触数)
- 学校訪問状況、説明会参加者数、SNSでの認知度向上施策など。
- 自社イベント(院内見学会など)への誘導数・参加数
- 選考(面接)移行数
- 内定数
- 内定承諾数(採用数)
- 各フェーズの移行率
これらの数値を日々、あるいは定期的に確認し、進捗を把握することで、どこにボトルネックがあるのかを特定し、改善に繋げることができます。採用担当者の仕事は、母集団の最大化とイベント誘導の最大化であり、年間計画に基づいたイベント企画や求人媒体の最適化なども含まれます。
✅3. 魅力的な情報発信と、求職者の「知りたい」に応える
現代の求職者は、就職先を選ぶ際に多岐にわたる情報を求めています。企業情報や仕事内容はもちろん、理念・ビジョン、事業の安定性・将来性、社会貢献、経営者の人柄、ロールモデル、具体的な働き方、キャリアパス、福利厚生、研修制度・育成方針など、様々な「知りたい」が内在しています。
貴院の採用サイトやSNSでは、これらのニーズに応えるコンテンツを充実させることが重要です。例えば、以下のような情報を積極的に発信しましょう。
📌仕事内容や院のコンセプト
どんなサービスを提供しているのか、求職者に明確に示すことで、仕事のイメージを明確にする。貴院が患者様にどのような考えを持って施術を提供しているのかを明確にする「治療コンセプト」も重要です。
📌「人」に関する情報
自社の人間関係、スタッフの働き方、モデル社員のインタビューなど、どのような人が働いているのかを示すことで、求職者は入社後のイメージを具体的に持つことができます。院長やスタッフの顔写真、患者様とのツーショット写真の掲載も有効です。
📌研修・教育体制
「見て覚えろ(盗め)」の時代は終わり、教育を仕組み化し、一流の施術家になるまでの道筋を示す必要があります。新人教育では、目指すべき人材像を知識・スキル・マインドの各テーマで設定し、それを伸ばす教育計画を策定することが重要です。スキルアップ制度、マンツーマンフォロー制度、キャリアステップ制度、独立開業支援制度など、具体的なフォロー体制を明示しましょう。無資格者が中心の業態であっても、常に復習ができ、フィードバックできる体制を整えることが大切です。
📌働き方の多様性
近年、拘束時間や休日、リモートワーク、フレックスタイム制など、柔軟な働き方を求めるニーズが高まっています。こうした多様な働き方への対応を明確にすることで、魅力度を高めることができます。
また、情報発信においては、読者の心理(ニーズ)を深く理解し、その商品・サービスを使うことでどんな未来を得られるのか(ベネフィット)を伝える「シズル感」のあるキャッチコピーを用いることが重要です。「これは広告ではありません」といった表示があっても、掲載料を支払っている口コミサイトやランキングサイトは広告として扱われる場合がある点にも注意が必要です。
一次情報、つまり貴院が独自に保有する情報や直接体験で得た情報を鮮度良く提供することも、信頼性を高める上で非常に有効です。例えば、Googleマイビジネスでは、院の内観や外観、コロナ感染対策の写真なども含め、地域で一番写真の登録数を多くすることを目指しましょう。Googleマップの口コミは、患者様の来院決定に大きく影響するため、積極的に集め、内容を分析してサービス改善に繋げることが大切です。
✅4. 入社前から「組織人」としての定性評価基準を共有する意義
入社前の段階から、貴院が「組織人」として求める行動やスタンスを明確に共有することは、入社後のミスマッチを防ぎ、スムーズな立ち上がりを促す上で非常に有効です。貴院の「経営計画書」などを活用し、社員に「素直」「自立」「自律」「誠実」「謙虚」といった定性的な評価項目を伝えていきましょう。
- 素直(Sunao): 成果の出ているやり方をそのまま真似できること。自身の小さなプライド(自分が一番正しいという姿勢)を捨て、成果にこだわる姿勢が本当のプライドであることを伝えましょう。「素直が成長のカギ」とも言われます。
- 自立(Jiritsu): 自分の仕事に責任を持ち、仕事への評価を受け入れて改善できること。仕事は常に第三者から評価されるものです。
- 自律(Jiritsu): 自分の機嫌は自分で取り、自分の気分や好き嫌いで仕事をしないこと。
- 誠実(Seijitsu): 言葉と行動が一致していること。言動一致は自信に繋がります。
- 謙虚(Kenkyo): 他人の短所だけでなく自身の完璧でない部分も認識し、周囲に感謝する姿勢は、チームの人間関係を良好にし、自身の成長にも繋がります。
これらは、社会人として当たり前に求められる「挨拶」や「報連相」といった項目から始まり、責任感、チャレンジ意欲、チームワークなど、組織に貢献するために必要なスタンスを示します。これらの「会社が喜ぶこと」や「会社の理念に基づいた行動」を共有することで、代表もスタッフも共に喜び、会社の成長に貢献するという意識を高めることができます。社員が「決められたことを決められた通りに実行し責任を果たす」という組織の基本機能を理解することは、個人と集団でより大きな目標を達成するために不可欠です。
これらの基本的な対策を徹底することで、内定辞退のリスクを低減し、貴院の未来を共に築く素晴らしい仲間を迎え入れる土台が作れるはずです。
▼無料相談(60分・オンライン/対面)を予約する▼
5. 内定辞退を防ぐ!具体的なコミュニケーション術
内定を出した優秀な人材に、どうすれば「この院で働きたい!」と強く思ってもらえるでしょうか?大切なのは、内定者との間に「共感」と「信頼」を育むことです。一方的な情報提供ではなく、双方向のコミュニケーションで、彼らが抱える不安を解消し、入社後の具体的なイメージを描けるようにサポートしていきましょう。
✅内定者と「共感領域」を育むためのコミュニケーション
採用において、私たちは「能力」以上に「価値観(考え方)」を共有できる人材を重視しています。まさに「理念共感型採用」こそが、組織の純度を高め、共に成長できる仲間を集める鍵となります。面接の段階から、貴院の「行動理念」を明確に伝え、「時間やお金の交換」だけを求める働き方であれば、もっと楽な場所もあると正直に伝える姿勢も大切です。これにより、本当に貴院の理念に共感し、長く活躍してくれる人材との出会いに繋がります。
人間らしい「あたたかい場所」を目指す組織は、「優しさ」と「強さ」を両立しています。経営者として孤独を感じることもあるかもしれませんが、スタッフを愛し、スタッフに愛される組織こそが理想の形です。内定者とのコミュニケーションでは、彼らの内面に深く入り込み、どんな悩みや不安、そしてどんな「なりたい姿」を持っているのかを「共感」の姿勢で引き出しましょう。
✅定期的な個別面談や交流イベントの開催
内定者との関係性を深めるには、定期的な接点が不可欠です。
- 個別面談: 面談は、単なる情報共有の場ではありません。内定者が抱える疑問や不安を解消し、彼らが「どんな風に成長したいか」「どんな働き方をしたいか」といった将来のビジョンを具体的に描くための「きっかけ」となる場です。院長や代表との個別面談は、内定者の心理的安全性を高め、会社への信頼感を築きます。面談の際は、必ず事前に準備をし、始まりと終わり時間を決めて臨みましょう。面談を通じて、期待と現実のギャップを埋め、モチベーション向上に繋がる「フィードバック」を丁寧に行うことが大切です。
- 交流イベント: 社内イベントや懇親会は、内定者が貴院の「人」や「雰囲気」を知る貴重な機会です。新人歓迎会はもちろん、ペア院懇親会、社員総会、運動会、BBQ、忘年会、社員旅行など、様々な企画で内定者と既存スタッフとの接点を増やしましょう。中にはスタッフが自発的に誕生日サプライズを行うような院もあり、こうした温かい文化は内定者の心にも響くはずです。イベントを通じて、仕事以外の顔を知り、普段話せない人とのコミュニケーションが生まれることで、入社への期待値は大きく高まります。
✅「タテ・ヨコ・ナナメ」の関係性を築くための先輩社員との交流
内定者が安心して入社するためには、院内の人間関係の「雰囲気の良さ」が重要な決め手の一つとなります。経営者や院長だけでなく、様々な立場の先輩社員との交流を促し、「タテ(上司・部下)」「ヨコ(同期・同僚)」「ナナメ(他部署・他院の先輩)」の関係性を築くことが大切です。
貴院の行動理念にある「健全な上下関係のある人間関係を構築し、全員が利他の精神を持つ粋なチーム」を目指しましょう。同僚への配慮や部署間の良好な関係性は、組織の活性化に不可欠です。また、「自立した人間同士が連帯することで、化学反応、シナジー効果が生まれる」という考え方を共有し、共に助け合い、切磋琢磨しながら成長できる仲間がいることをアピールすることで、内定者の入社意欲はさらに高まるでしょう。
✅キャリアパスの明確化と、入社後の具体的な成長イメージの共有
「この院で、私はどうなれるのだろう?」という内定者の問いに、具体的に答えることができれば、不安は期待へと変わります。社員の定着率を上げるためには、「キャリアパスの多様化」が非常に重要です。
- 明確なキャリアプランの提示: 院長、マネージャー、専門職など、貴院にはどのようなキャリアの選択肢があるのかを明確に伝えましょう。入社後の3〜5年で目指せる具体的な「経営ビジョン」を共有し、そこに至るまでの組織図や各役職に求められる業務レベルを詳細に説明します。
- 教育プログラムの整備と共有: 「教育体制の構築」は、組織が発展するための重要な要素です。新人教育では、「目指すべき人財像」を知識・スキル・マインドの各テーマで設定し、具体的な教育計画を策定することが必要です。単に「見て覚えろ」ではなく、一流の施術家になるまでの道筋を「仕組み化」して示すことが求められています。
- 成長と貢献の実感: 「自分が育ててもらったのだから後輩を教育する」という「恩送り」の文化、そして「報連相」や「挨拶」といった基本的な「組織人」としての姿勢、さらには「リーダーシップ」や「部下育成」といった「管理職」としてのスキルを段階的に身につけていけることを伝えます。これらが、等級手当や役職手当といった報酬にどう繋がるのかを明確にすることで、内定者は入社後の具体的な成長イメージと、それによる貢献実感を抱くことができます。
✅気軽に相談できる環境の整備(チャットワークなどの活用)
内定者が入社まで、そして入社後も「いつでも相談できる」という安心感は、定着に大きく影響します。「相談しやすい雰囲気」を作ることは、上司への信頼を築く上で非常に重要です。
- オープンなコミュニケーション: 些細な疑問でも、すぐに相談できる体制を整えましょう。「愚痴」はストレスになりますが、困っていることは積極的に上司や先輩に「相談」するよう促す文化を醸成します。
- デジタルツールの活用: チャットワークのようなツールを導入し、内定者と既存スタッフ、またはコンサルタントとの間で気軽にコミュニケーションが取れる環境を整備することも有効です。これにより、物理的な距離があっても、心理的な距離を縮めることができます。また、社員が意見やアイデアを出しやすい「仮説研修」などの場を設け、経営陣が直接耳を傾ける機会を作ることで、彼らは「自分の声が届く」と感じ、主体性が育まれます。
6. よくある質問
内定者が入社を決める上で、必ず出てくるのが「不安」や「疑問」です。これらに誠実かつ具体的に答えることで、信頼関係をさらに強固にできます。
✅内定者が不安に感じやすいこととその解消法
- 「仕事についていけるか不安…」
貴院の充実した「教育プログラム」を具体的に説明しましょう。例えば、「入社後3ヶ月間の新人研修では、基礎から丁寧に指導し、先輩社員がマンツーマンでサポートします。定期的な勉強会や技術チェックで、未経験からでも安心して成長できる環境です。」と伝えます。特に「初心者にもやさしく指導」されることは、内定者の安全の欲求を満たします。 - 「職場の人間関係が合うか心配…」
「現場の人間関係が円滑」であることは、離職防止の重要ポイントです。社内イベントや部活動、定期的なチームビルディングの機会を通じて、「同世代の仲間も多く、風通しの良い職場です」と具体例を交えて伝えましょう。 - 「ワークライフバランスは取れるのか…」
「適正な労働時間」や「適正な休暇取得」を保証していることを明示します。例えば、「週休2日制を導入しており、有給休暇も計画的に取得可能です。プライベートも充実できる環境です」といった具体的な制度を伝え、福利厚生もしっかり完備されていることを強調します。
✅他社からの引き抜きや比較への対応
現代は採用競争が激化しており、他社との比較は避けられません。貴院ならではの「差別化要素」を明確に伝えましょう。
- 貴院の強みを具体的に:
- 商品力: 「当院独自の整体技術は、他の治療家も学びにくるほど注目されています。」
- 専門性: 「女性専門整体」「巻き爪・外反母趾専門」「小顔専門」など、特定のニーズに特化した業態展開を行っている場合、その優位性を伝えます。
- 治療コンセプト: 「再発しない身体づくり」など、貴院の治療コンセプトを明確に定義し、「当院でしかできないこと」を具体的に説明できるように、トークスクリプトなどを活用してスタッフ全員で品質を統一することが重要です。
- 患者様への価値提供: 「患者様のお身体の状態をくまなくチェックし、一人ひとりにベストな施術計画を作成します。痛みの根本原因を解消し、その先にある理想の生活までサポートするのが当院の強みです。」目に見えないサービスを「見える化」するための工夫も有効です。
- キャリアパスの魅力: 「多店舗展開や多業態展開により、キャリアパスの選択肢が豊富です。」若くても役職につける、多様な経験ができるといった具体的なキャリアイメージを伝えることで、「ここでなら長く働ける」と感じてもらえるでしょう。
- 給与・待遇: 他社と比較された場合でも、「社員への還元を積極的に行っている」という姿勢を伝え、基本給の安定性、公正な評価制度に基づく昇給・昇格の仕組みがあることを明確に説明します。
✅給与や待遇に関する質問への具体的な回答例
給与や待遇に関する質問は、内定者が最も気にするポイントの一つです。誠実かつ具体的に回答しましょう。
- 基本給と各種手当: 「基本給は〇〇円からスタートし、住宅手当や資格手当など、各種手当も充実しています。社員の皆さんが安心して働けるよう、社会保険も完備しています。」
- 評価制度と昇給・昇格: 「当院では、年4回の査定を通じて、皆さんの成果や人間性を公正に評価し、給与や賞与に反映しています。具体的には、施術技術の向上はもちろん、患者様とのコミュニケーション、チームへの貢献度など、多角的に評価します。「成果を出すためのやり方」を具体的に指導し、着実に成長し、ステップアップできる環境です。」
- キャリアアップと連動した報酬: 「等級制度(キャリアパス)を導入しており、役職が上がるにつれて職能給や役職手当が支給されます。例えば、入社3年で副院長を目指し、さらにマネージャーへとキャリアアップすることで、年収〇〇万円も可能です。社員の皆さんの成長が会社の成長に直結し、それが還元される仕組みを大切にしています。」
7. まとめ
本コラムでは、人材の定着やモチベーションアップ、サービスの品質均一化、若手育成といった整骨院経営者が抱える「組織力」に関するお悩みを解決するためのヒントをお伝えしてきました。
人材採用競争が激化する現代において、内定辞退を防ぎ、貴院が求める優秀な人材を確保し、長く活躍してもらうことは、事業拡大と永続的な成長に不可欠です。そのためには、内定者との「共感」を育むコミュニケーション、定期的な個別面談や交流イベントによる信頼関係の構築、「タテ・ヨコ・ナナメ」の関係性を築く先輩社員との交流、そして明確なキャリアパスと具体的な成長イメージの共有が重要です。さらに、気軽に相談できる環境を整備し、内定者の不安を一つ一つ解消していく丁寧な対応が、最終的な入社へと繋がります。
内定者一人ひとりが「この院で働きたい」と心から思えるような、魅力的で「人」を大切にする組織づくりを進めていきましょう。
8. 新卒採用で困ったときの相談先
「コラムを読んで、組織づくりの重要性は分かったけれど、具体的に何をどう進めればいいか…」そうお感じになった経営者の方もいらっしゃるかもしれません。ご安心ください。私たち船井総合研究所は、貴院の経営を力強くサポートいたします。
私たちは、「社会的価値の高い理念」のもと、持続的成長を続ける「グレートカンパニー」の実現を目指し、治療院特化型のコンサルティングチームとして、日々の現場で培った「生きたノウハウ・理論」を提供しています。
船井総研の整骨院経営研究会、交通事故研究会のご紹介
貴院の悩みに合わせて、専門性の高い研究会をご用意しています。
- 整骨院経営イノベーション研究会: 自費治療導入やマネジメント分野に特化し、貴院の生産性向上と業績アップを強力に支援します。
- 整骨院交通事故研究会: 交通事故治療に特化し、最新の集患ノウハウから患者様対応、保険会社との連携まで、実践的な情報を提供します。交通事故治療は、患者様の身体的・経済的・精神的苦痛を救う、社会的意義の大きい分野です。医接連携を通じて、患者様に安心と信頼を提供し、適正な期間での回復を目指すことをサポートします。
貴院の「こうなりたい」というビジョンを私たちに聞かせてください。私たちは、経営者の夢を実現するため、「なんとしても支援先の業績を向上させる」という情熱をもって伴走いたします。
▼無料相談(60分・オンライン/対面)を予約する▼
まずは無料個別相談で整骨院経営のお悩みを解決!

弊社の整骨院・接骨院・整体院の経営専門のコンサルタントが、初回のみ無料で個別相談をご対応させて頂きます。
・売上を伸ばしたいが、何から始めればいいのかわからない
・患者様数を増やしたいが、何から始めればいいのかわからない
・採用をしたいが応募が全然こない
・事業拡大に伴い、育成環境や評価制度を整備したい
など、様々な経営のお悩みに対応しております。
是非、無料個別相談をご活用ください。
船井総研ならではの治療院経営の現場最新情報&ノウハウが満載の無料メールマガジン
自費治療で売上が月200万円以上UP!新規交通事故患者が毎月8名以上集まる!
その秘密を無料メルマガで大公開!!