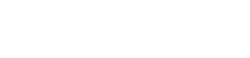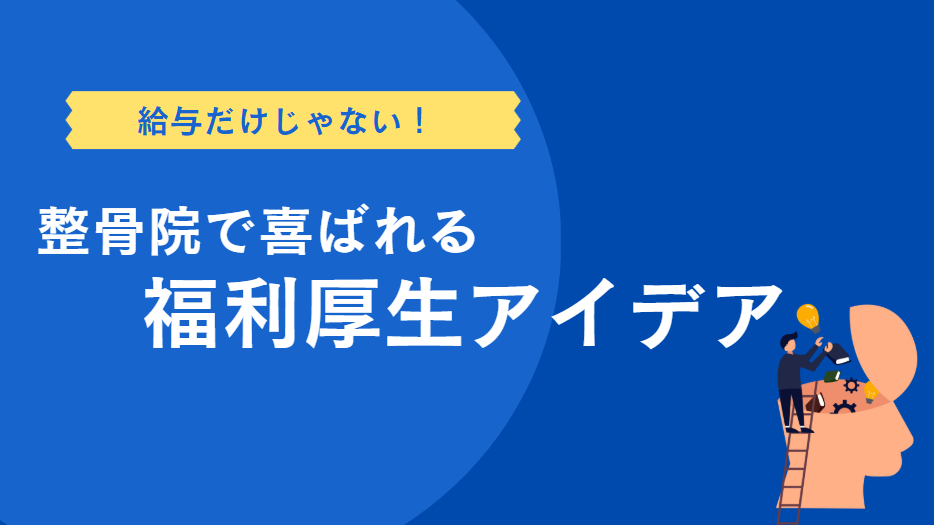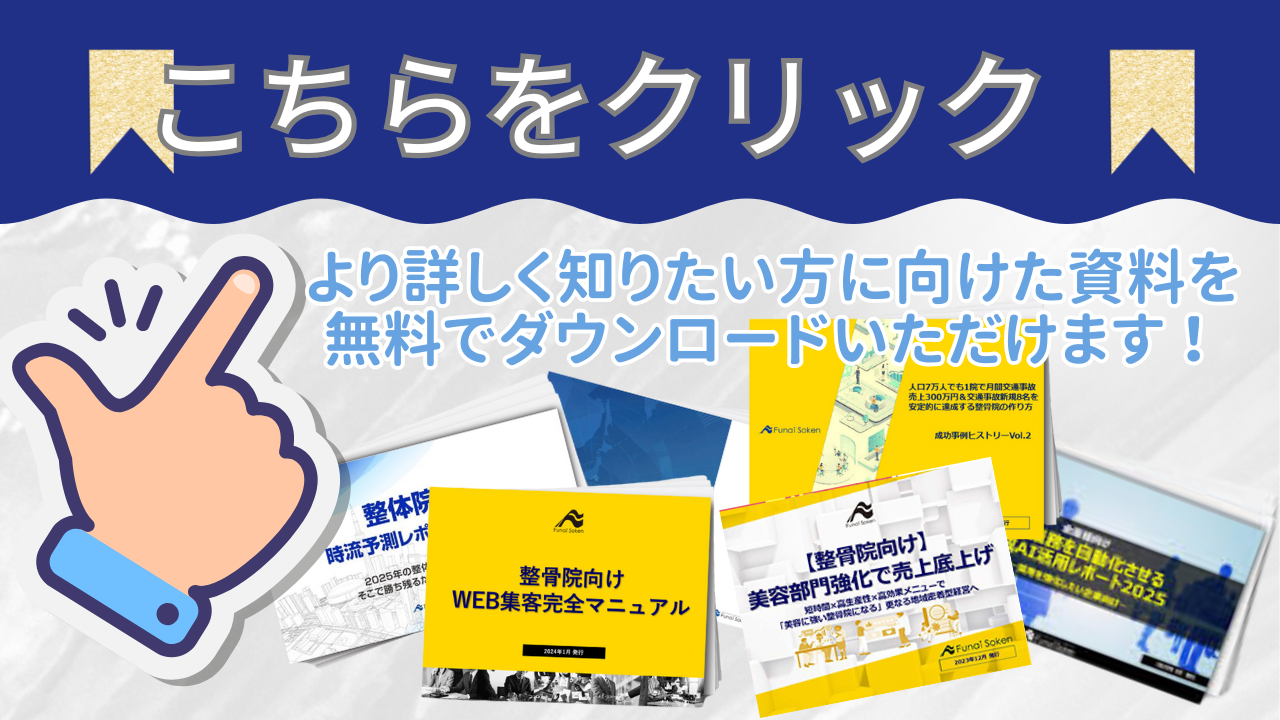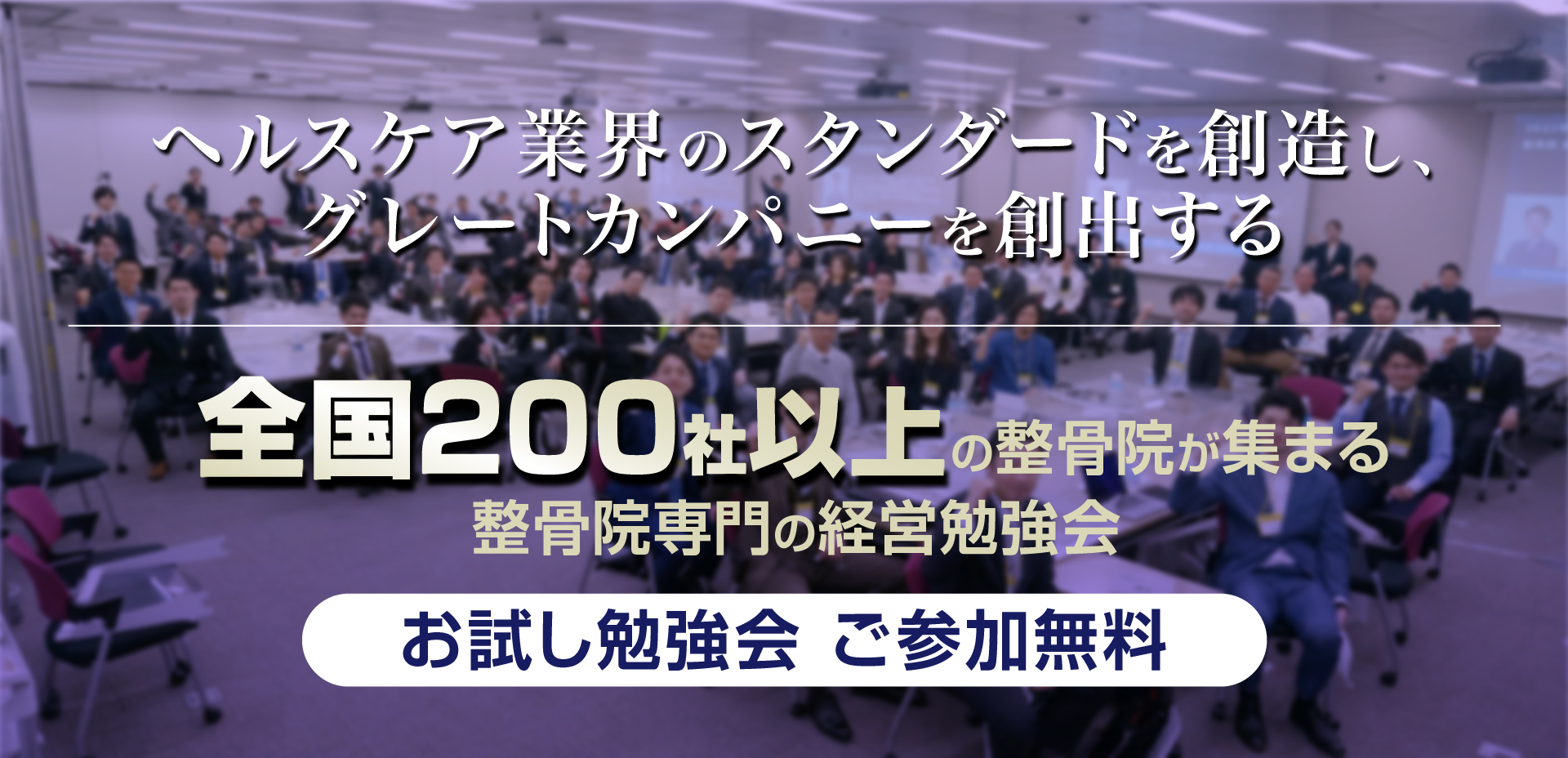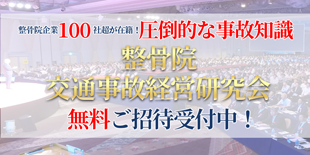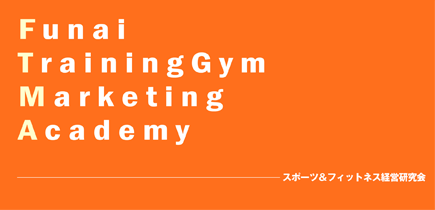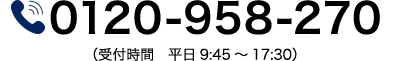Table of Contents
給与だけじゃない!整骨院で喜ばれる福利厚生アイデア
1. この記事はこんな方におすすめ
整骨院の経営者の皆様、日々の業務、本当にお疲れ様です。患者様への施術はもちろんのこと、スタッフの採用、育成、そして日々の院運営と、多岐にわたる業務をこなされていることと存じます。
特に、下記のようなお悩みをお持ちではないでしょうか?
✓「せっかく求人を出しても、なかなか優秀な人材が集まらない…」
✓「採用できたとしても、スタッフが長続きせず、定着率が低いことに悩んでいる…」
✓「給与や待遇面以外で、スタッフのモチベーションをどう高めれば良いのか、具体的なアイデアが欲しい」
✓「スタッフが活き活きと長く働ける、働きがいのある職場環境を築いて、もっと良い院にしていきたい!」
✓「組織全体のパフォーマンスを高め、会社への貢献度をもっと引き上げたいけれど、何から手をつければ良いのか…」
もし、あなたがこのようなお悩みを一つでもお持ちでしたら、このコラムはきっとお役に立てるはずです。
このコラムでは、スタッフが「ここでずっと働きたい!」と心から思えるような、給与だけではない「働きたくなる福利厚生」について、具体的なアイデアと実践のヒントを惜しみなくお伝えしていきます。
2. 「働きたくなる福利厚生」とは?
「福利厚生」と聞くと、皆さんは何を思い浮かべるでしょうか?住宅手当、交通費支給、社会保険完備といった、いわゆる「法定福利厚生」や、有給休暇、健康診断などの一般的な「法定外福利厚生」を想像されるかもしれませんね。もちろん、これらはスタッフが安心して働くための基本であり、非常に大切です。
しかし、今回お伝えしたい「働きたくなる福利厚生」は、給与や一般的な待遇だけでは満たされない、スタッフの「心の満足」や「成長」に深く関わるものを指します。
心理学には「二要因理論」という考え方があります。これによると、人の満足には「衛生要因」と「動機付け要因」の2種類があると言われています。
✅衛生要因: 給与、労働時間、職場環境、人間関係など。これらが不足すると不満が生じますが、満たされても「積極的に満足する」わけではありません。例えるなら、不満を減らすための「最低限の土台」です。
✅動機付け要因: 仕事の達成、承認、責任、成長、貢献、患者様との良好な関係など。これらは満たされると「やる気や幸福感」が増し、積極的に仕事に取り組む原動力となります。例えるなら、スタッフを「前向きに動かすエンジン」です。
つまり、「働きたくなる福利厚生」とは、単に「不満をなくす」だけでなく、スタッフが「ここで働き続けたい!」と心から思えるような、「動機付け要因」を満たし、主体的な成長と貢献を促す職場環境や制度づくりのことなのです。
具体的には、以下のような要素が挙げられます。
- キャリアアップと成長の機会:
- 外部セミナーへの参加支援や、専門技術を深めるための社内研修・勉強会の充実。自己資金でセミナーに参加していた経験がある経営者の事例にもあるように、会社からの投資はスタッフの「期待されている」という気持ちに繋がります。
- 明確なキャリアパス(主任、院長、マネージャー、さらには独立支援など)の提示と、それに応じた教育プログラムの整備。
- 良好な人間関係と働きやすい環境:
- 「タテ・ヨコ・ナナメ」といった多様なコミュニケーション経路の確立と、困ったときに相談しやすい心理的安全性の高い職場づくり。
- 適切な労働時間や休暇取得の推進、ハラスメント防止策の徹底。
- 自発的な誕生日サプライズや社内懇親会、お花見イベントなど、スタッフ間の絆を深める取り組み。
- 公正な評価と貢献実感:
- 個人の頑張りや成果が正当に評価され、給与や役職に反映される透明性の高い評価・賃金制度。
- 患者様からの感謝の声や、院の目標達成への貢献を通じて「誰かの役に立っている」という実感が得られる仕組み。会社への貢献がスタッフ自身の喜びにも繋がる状態を目指します。
- 多様な働き方への対応:
- スタッフそれぞれのライフステージやキャリアプランに合わせた、柔軟な勤務形態(時短勤務、休日の選択制など)の導入検討。
このような「働きたくなる福利厚生」を充実させることは、スタッフ一人ひとりのモチベーションを高め、離職率を低下させ、定着率を向上させるだけでなく、結果として組織全体の生産性アップ、サービスの質の向上、そして患者様満足度の向上にも直結し、安定した院経営の基盤となります。
3. 対策を取らないとどうなる?放置リスクと現実的な課題
「働きたくなる福利厚生」の重要性をご理解いただけたかと思いますが、では、もしこれらの取り組みを「後回し」にしたり、「一般的なことだけやっていれば良い」と放置してしまったりすると、どのようなことが起こるのでしょうか?
残念ながら、その影響は決して小さくありません。一時的な問題にとどまらず、整骨院経営の根幹を揺るがす深刻な事態に発展する可能性も秘めています。
具体的なリスクと課題を見ていきましょう。
📌(1) スタッフのモチベーション低下と生産性の停滞
パート2で触れた「衛生要因」だけが満たされ、「動機付け要因」が不足している状態が続くと、スタッフは積極的に仕事に取り組む意欲を失ってしまいます。「どうせ頑張っても評価されない」「成長の機会がない」と感じると、指示されたことだけをこなす「受け身」の姿勢になりがちです。これにより、一人ひとりのパフォーマンスはもちろん、組織全体の生産性も低下し、院の成長スピードが鈍化してしまいます。
📌(2) 離職率の増加と採用難の加速
スタッフが「ここで働き続けたい」と思えなければ、より良い環境を求めて離職してしまいます。特に、整骨院業界は慢性的な人手不足の課題を抱えており、離職率が高い状態は、新たな人材採用をさらに困難にします。
「採用の失敗は、教育で取り返せない」という言葉があるように、一度採用に失敗すると、組織の純度が低下し、悪循環に陥ることもあります。また、退職者が出るたびに、求人広告費用や採用活動にかかる時間、新しいスタッフへの教育コストが増大し、経営を圧迫します。これは、新規患者の集患コストが増加し、施術所数が増える一方で療養費が減少傾向にある現在の業界時流と相まって、新規患者を集めるだけでは売上向上に繋がりづらい状況をさらに悪化させます。
📌(3) サービスの質低下と患者様満足度の低下
経験の浅いスタッフや、モチベーションの低いスタッフが増えると、施術の質や患者様への対応にも影響が出かねません。例えば、技術の統一が不十分だったり、患者様の真のニーズを引き出すカウンセリングがおろそかになったりする可能性があります。患者様は、痛みの改善だけでなく、安心して通える環境やスタッフとの信頼関係を求めています。質の低いサービスは患者様からの不満に繋がり、悪い口コミ(レビュー)に繋がる可能性もあります。これは、新規患者の獲得にも悪影響を及ぼし、結果的に来院数の減少や売上低下を招くことになります。
📌(4) 組織の一体感の喪失と理念の形骸化
「会社への貢献がスタッフ自身の喜びにも繋がる状態」を目指すことが「働きたくなる福利厚生」の目的の一つですが、これが実現できないと、スタッフは会社や院のビジョンに共感できず、「自分のため」だけの仕事になりがちです。経営計画書で「全員が納得満足できる施策はない。『成長したい人が成長できる組織』にする」と示されているように、会社が成長するための理念やビジョンを共有できていないと、組織はバラバラになり、一体感を失ってしまいます。結果として、院の目指す方向性や「らしさ」が曖昧になり、患者様にも伝わりにくくなってしまうでしょう。
📌(5) 経営者の負担増大と疲弊
常にスタッフの採用や育成、トラブル対応に追われることで、経営者自身が本来集中すべき「未来の業績創り」や「ビジョン策定・組織づくり」といった戦略的な業務に時間を使えなくなってしまいます。「自分が満たされていない状態でスタッフに愛を与え続けるのは本当にしんどい」という経営者の声もあるように、スタッフの課題が山積すると、経営者自身のメンタルヘルスにも悪影響を及ぼし、経営そのものの持続可能性が危ぶまれる事態に陥る可能性もあります。
これらのリスクを回避し、持続可能な整骨院経営を実現するためには、「働きたくなる福利厚生」への投資は、単なるコストではなく、未来への重要な投資であると捉えることが不可欠です。
4. まず取り組みたい基本的な「働きたくなる福利厚生」対策
スタッフのモチベーションを高め、離職を防ぎ、定着率を向上させる「働きたくなる福利厚生」は、決して特別なことばかりではありません。日々の経営の中で意識し、小さなことからでも着実に実践していくことが大切です。
ここでは、特に重要で、比較的取り組みやすい基本的な対策を4つの柱としてご紹介します。
🔹(1) 理念・ビジョンの共有と「成長できる組織」の土台づくり
経営の根幹となるのは、「何のためにこの院が存在するのか」「どこを目指しているのか」という理念やビジョンの明確化と、その共有です。経営計画書にあるように、「全員が納得満足できる施策はない。『成長したい人が成長できる組織』にする」という方針は、まさにスタッフの成長意欲を刺激する土台となります。
- 「スタッフが成長しながら笑顔で長く働ける会社」という経営コンセプトを掲げ、これを実現するための組織づくりを進めましょう。
- スタッフ一人ひとりのビジョンと会社のビジョンが重なる「共感領域」を創出することが重要です。この「共感領域」が大きければ、スタッフは自分の努力が会社の成長に繋がり、会社の成長が自身の喜びにも繋がる、という貢献実感を持ち、モチベーションが維持されます。
- 会社の理念やビジョンに基づいた行動が、会社もスタッフも喜ぶ結果に繋がることを意識し、「会社のためになること」を追求しましょう。
- 「早く行きたいなら一人で行け、遠くに行きたいならみんなで行け」という言葉があるように、責任と役割を分担することで、個人では達成できないことを組織として達成することを目指します。
🔹(2) 体系的な「人財育成」の仕組み
スタッフの成長をサポートする環境は、「働きたくなる福利厚生」の「動機付け要因」の中核をなします。特に整骨院業界は変化のスピードが速く、常に「バージョンアップ」が求められる時代です。
- 教育への投資を惜しまない: 経営者自身の「分院長時代に全く教育にお金をかけてもらえなかった」という経験からくる「社会人の親は経営者」という考え方で、スタッフに学びの機会を提供することが重要です。外部セミナーへの参加支援や、専門技術を深めるための社内研修・勉強会を充実させましょう。外部に出ることで自身の立ち位置やレベルを知り、マンネリ防止にも繋がります。
- 明確なキャリアパスと教育プログラム: 主任、院長、マネージャー、さらには独立支援など、明確なキャリアパスを提示し、それに応じた教育プログラムを整備します。
- マニュアルの積極的な活用: マニュアルはサービスの均一化だけでなく、スタッフが仕事で成果を出しやすくするための「攻略本」です。成果を出している人のやり方をそのままマニュアルやスクリプトにし、全社に周知することで、全員が「勝ちやすい」状態を作り出します。特に、技術の統一が不十分でスタッフによって言うことが違う、といった課題を解消するためには、マニュアルは不可欠です。動画を活用して説明の質を統一し、効率を高めることも有効です。
- 新人研修の充実: 新人の離職防止のためには、目指すべき人材像を明確にし、知識・スキル・マインドの各テーマで教育計画を策定することが重要です。
🔹(3) 心理的安全性と「働きがい」を高める環境づくり
スタッフが安心して、意欲的に働ける環境を整えることは、パフォーマンス向上に直結します。
- 多様なコミュニケーション経路の確立: 「タテ・ヨコ・ナナメ」といった多様なコミュニケーション経路を確立し、困ったときに相談しやすい心理的安全性の高い職場を作りましょう。特に「ナナメ」の関係は、同僚には話しにくいが上司には直接言いにくい、といった悩みの解決に非常に有効です。
- 働き方の柔軟性: スタッフそれぞれのライフステージやキャリアプランに合わせた、柔軟な勤務形態(時短勤務、休日の選択制など)の導入を検討しましょう。
- 労働環境の適正化: 適切な労働時間や休暇取得の推進、ハラスメント防止策の徹底は、基本的な「衛生要因」として非常に重要です。
- 社内イベントや交流の活性化: 自発的な誕生日サプライズや社内懇親会、お花見イベントなど、スタッフ間の絆を深める取り組みは、職場の雰囲気を良好に保ち、一体感を醸成します。
🔹(4) 成果を「見える化」する評価・フィードバック
スタッフの頑張りが正当に評価され、それが自身の成長や処遇に繋がっているという実感は、大きなモチベーションになります。
- 透明性の高い評価・賃金制度の導入: 個人の頑張りや成果が正当に評価され、給与や役職に反映される透明性の高い評価・賃金制度を整備しましょう。
- 評価項目と業績の連動: 評価項目を「組織目標」「個人目標」「重点行動」「専門性」「組織行動」「マネジメント」の6つに分類し、特に「重点行動」を盛り込むことで、評価が個人の業績アップに直結するように設計しましょう。
- 成果の「見える化」とフィードバック: スタッフが上げた成果や成績を「見える化」し、定期的にフィードバックを行うことで、達成感ややりがいを明確に感じさせることが重要です。自己評価と上長評価のすり合わせは、スタッフの成長を促す上で非常に効果的です。
- 貢献実感の醸成: 患者様からの感謝の声や、院の目標達成への貢献を通じて、「誰かの役に立っている」という実感が得られる仕組みを作りましょう。
これらの基本的な対策を継続的に実施することで、スタッフは「この院で働き続けたい」と心から思えるようになり、結果として、サービスの質の向上、患者様満足度の向上、そして持続可能な院経営へと繋がっていくでしょう。
5. よくある質問 (FAQ)
これまでの内容を読んで、さらに疑問に思ったことや、より具体的な実践方法について知りたいという声も多いかと思います。ここでは、整骨院経営者の皆さんが抱えやすい、福利厚生や組織づくりに関するよくある質問にお答えしていきます。
Q1:スタッフの「ここで働き続けたい!」という気持ちを育むには、何が一番大切ですか?
A1: スタッフが「ここで働き続けたい!」と心から思うためには、「衛生要因」と「動機付け要因」の両方をバランス良く満たすことが非常に重要です。
- 「衛生要因」とは、給料、労働時間、労働環境、評価制度など、不満を招く要因を取り除くためのものです。これらが不足していると不満に繋がりますが、満たされたからといって「積極的な満足」が増加するわけではありません。しかし、これらが適切であることは、スタッフが安心して働くための土台となります。
- 「動機付け要因」こそが、スタッフの「働きがい」や「満足感」を直接高めるものです。具体的には、院のミッションへの共感、目標達成や承認、患者様との良好な関係、自身の成長、貢献実感、責任感などが挙げられます。
特に大切なのは、「スタッフが成長しながら笑顔で長く働ける会社」という経営コンセプトのもと、スタッフ一人ひとりのビジョンと会社のビジョンが重なる「共感領域」を創出することです。自分の努力が会社の成長に繋がり、会社の成長が自身の喜びにも繋がる、という貢献実感を持てる環境こそが、長期的な定着に繋がります。経営者は「社会人の親」という想いで、社員に学びの環境を提供することも重要です。
Q2:スタッフの技術レベルを統一し、サービスの質を保つにはどうすれば良いですか?
A2: 技術の統一とサービス品質の維持には、体系的な「人財育成」の仕組みとマニュアルの積極的な活用が不可欠です。
- マニュアルの徹底活用: マニュアルは単なるサービスの均一化のためだけでなく、スタッフが仕事で成果を出しやすくするための「攻略本」です。成果を出している人のやり方をそのままマニュアル化し、全社に周知することで、誰もが「勝ちやすい」状態を作り出せます。特に、技術の統一が不十分でスタッフによって言うことが違う、といった課題を解消するためには、マニュアルは極めて重要です。
- 動画の活用: 説明の質を統一し、効率を高めるためには、動画を活用した教育も非常に有効です。例えば、患者様への説明動画を共有することで、施術者の説明のばらつきをなくし、成約率の差をなくすことができます。
- 継続的な研修とフィードバック: 新人研修を充実させ、目指すべき人材像を明確にした上で、知識・スキル・マインドの各テーマで教育計画を策定することが重要です。また、外部セミナーへの参加支援を通じて、スタッフが自身の立ち位置やレベルを知り、マンネリ化を防ぐことも効果的です。
Q3:スタッフが積極的に意見を言い、安心して働ける職場環境を作るには?
A3: スタッフが安心して、意欲的に働ける環境、すなわち「心理的安全性」の高い職場を築くことが重要です。
- 多様なコミュニケーション経路の確立: 「タテ・ヨコ・ナナメ」といった多様なコミュニケーション経路を確立しましょう。
- 「ヨコ」の関係(同期・同僚)はガス抜きにはなりますが、問題解決には至りにくいことがあります。
- 「タテ」の関係(上司・部下)は解決に必須ですが、毎日顔を合わせるからこそ相談しにくい場合もあります。
- そこで「ナナメ」の関係(他院の院長、同部署の仲間など)が非常に有効です。言いやすさと問題解決力の両方が得られる可能性が高まります。
- 前向きな姿勢を尊重する: スタッフの前向きな提案に対し、一方的に却下せず、示唆的な質問でさりげなくフォローすることが大切です。これにより、「どうせ提案しても採用されない」という「学習性無力感」を与えないようにしましょう。
- 社内イベントの活性化: 自発的な誕生日サプライズや社内懇親会、お花見イベントなど、スタッフ間の絆を深める取り組みは、職場の雰囲気を良好に保ち、一体感を醸成します。
Q4:スタッフの頑張りを適切に評価し、モチベーションを高めるための評価制度のポイントは?
A4: スタッフの頑張りが正当に評価され、自身の成長や処遇に繋がっているという実感は、大きなモチベーションになります。
- 透明性の高い評価・賃金制度: 個人の頑張りや成果が給与や役職に反映される、透明性の高い評価・賃金制度を整備しましょう。
- 評価項目の明確化: 評価項目を「組織目標」「個人目標」「重点行動」「専門性」「組織行動」「マネジメント」の6つに分類し、特に「重点行動」を盛り込むことで、評価が個人の業績アップに直結するように設計しましょう。
- 成果の「見える化」とフィードバック: スタッフが上げた成果や成績を「見える化」し、定期的にフィードバックを行うことが重要です。自己評価と上長評価のすり合わせは、スタッフの成長を促す上で非常に効果的です。
- 段階的なキャリアパスの提示: 主任、院長、マネージャーなど、明確なキャリアパスを提示し、それに応じた評価や教育プログラムを整備することも、スタッフの長期的なモチベーション維持に繋がります。
Q5:患者様からの良い口コミを増やすにはどうすればいいですか?
A5: 患者様からの口コミは、新規患者様の獲得や院の信頼性向上に非常に大きな影響を与えます。
- 口コミの重要性の理解: Googleマイビジネスの口コミは、患者様が来院を決める際の重要な判断材料となります。口コミの数と評価が高い店舗は、信頼性が増し、検索ランキングにも良い影響を与えます。
- 積極的な口コミ収集: 良質な口コミは自然に増えるものではなく、積極的に集める必要があります。特に、交通事故患者様や通院歴が長く治療効果を感じている患者様など、良い口コミを書いてくれそうな方にお願いするのが効果的です。
- 口コミへの返信: 寄せられた口コミには、ポジティブなものだけでなく低評価のものにも真摯に返信しましょう。低評価の口コミは、サービス改善のための貴重なフィードバックとして捉え、改善に繋げることが重要です。
- 口コミの活用: 集まった口コミは、「お客様の声」としてウェブサイトや院内に掲載することで、さらに信頼性を高めることができます。業種やサービスごとに整理して掲載すると、より詳細な情報を伝えやすくなります。
6. まとめ&困ったときの相談先
これまでのパートで、整骨院経営における福利厚生の重要性から具体的な対策、そしてよくある質問への回答まで、多岐にわたる情報をお伝えしてきました。最後に、ここまでの内容を簡潔にまとめ、皆さんが「次の一歩」を踏み出すための具体的なサポートについてご案内いたします。
これまでのポイントを振り返りましょう
改めて、今回のコラムで最もお伝えしたかったポイントを振り返ってみましょう。
- 福利厚生は「投資」である: 優秀な人材の定着、採用競争力の向上、従業員満足度の向上、ひいては患者様へのサービス向上と売上アップに直結する重要な経営戦略です。単なる経費ではなく、未来への投資と捉えましょう。
- スタッフのモチベーションの源は「共感領域」: 給与や労働時間といった「衛生要因」だけでなく、院のミッションへの共感、成長や貢献の実感、責任感といった「動機付け要因」を満たすことが、「ここで働き続けたい」というスタッフの気持ちを育む上で最も大切です。経営者は「社会人の親」として、学びの環境を提供することが重要です。
- 人材育成と仕組み化が成長の鍵: 技術やサービスの質を統一し、安定的な経営を実現するためには、マニュアルの徹底活用や動画による教育、継続的な研修とフィードバックが不可欠です。特に、成果を出している人のやり方をマニュアル化し、社内で横展開することが重要です。
- 心理的安全性の高い職場環境: スタッフが安心して意見を言える環境(心理的安全性)を築くには、「タテ・ヨコ・ナナメ」の多様なコミュニケーション経路を確立し、前向きな提案を尊重する姿勢が求められます。社内イベントの活性化も絆を深める上で有効です。
- 透明性の高い評価制度: スタッフの頑張りを正当に評価し、モチベーションを高めるためには、個人の成果が給与や役職に反映される透明性の高い評価・賃金制度が必要です。成果の「見える化」と定期的なフィードバックが成長を促します。
- 患者様からの「声」を力に: 患者様からの良い口コミは、新規患者獲得や信頼性向上に不可欠です。積極的に口コミを収集し、ポジティブなものには感謝を、低評価には真摯な返信で改善に繋げましょう。
整骨院経営は、安定したニーズがある一方で差別化が重要となるビジネスです。市場全体としては予防市場も拡大しており、柔道整復師の増加による供給過多や不祥事の続発も懸念されています。このような時流の中、企業としての成長を持続させるためには、単に施術を提供するだけでなく、患者様の生活に入り込み、健康づくりやそれ以上の価値を提供する「先生業」へのアップデートも検討し、美容メニューや物販など多角的なサービス展開も視野に入れることが大切です。
困ったときの相談先
今回のコラムを読んで、「なるほど、実践してみよう!」と感じていただけた方もいれば、「自分の院の場合はどうすればいいのだろう?」「もっと具体的なアドバイスが欲しい」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
整骨院経営は、施術、教育、運営、経営と多岐にわたり、時には孤独を感じることもあります。しかし、決して一人で抱え込む必要はありません。
船井総合研究所では、整骨院経営者の皆様をサポートするための様々なサービスを提供しています。船井総研のコンサルティングは、現場に根差した「現場主義」、常に時流を捉える「時流適応」、クライアントの強みを伸ばす「長所伸展」、そして「過去オール善」の姿勢を大切にし、皆様の「最高の驚きをもたらす、すごい体験」を追求します。
無料個別相談
経営計画の策定、組織図の整理、採用戦略、幹部育成、出店計画など、事業拡大に関する具体的なサポートを提供しています。
まずは無料面談を下のURLからお申し込みください!
▼無料相談(60分・オンライン/対面)を予約する▼
経営研究会:
3か月に1回開催されるオンラインまたは弊社オフィスでの会員制勉強会です。
整骨院業界の最新情報、他業界のゲスト講師の講演、全国の会員様が持ち寄った成功事例を共有する「師と友づくり」の場として、多くの経営者にご参加いただいています。
「整骨院経営イノベーション研究会」や「整骨院交通事故研究会」など、テーマ別の研究会もございます。
貴院の具体的な目標達成のために、船井総研のノウハウと事例を最大限に活用し、最短最速で目標を達成できるようサポートいたします。
このコラムが、皆さんの整骨院経営における新たな一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
まずは無料個別相談で整骨院経営のお悩みを解決!

弊社の整骨院・接骨院・整体院の経営専門のコンサルタントが、初回のみ無料で個別相談をご対応させて頂きます。
・売上を伸ばしたいが、何から始めればいいのかわからない
・患者様数を増やしたいが、何から始めればいいのかわからない
・採用をしたいが応募が全然こない
・事業拡大に伴い、育成環境や評価制度を整備したい
など、様々な経営のお悩みに対応しております。
是非、無料個別相談をご活用ください。
船井総研ならではの治療院経営の現場最新情報&ノウハウが満載の無料メールマガジン
自費治療で売上が月200万円以上UP!新規交通事故患者が毎月8名以上集まる!
その秘密を無料メルマガで大公開!!